Young Researchers' Trip report
- 2012年度
- 第35回日本分子生物学会年会
(2012年12月13日~2012年12月14日) - Joint 12th International Child Neurology Congress(ICNC)
(2012年5月29日~2012年6月3日) - American Society for Cell Biology (ASCB) 2012 Annual Meeting
(2012年12月15日~2012年12月19日) - 第55回日本甲状腺学会学術集会
(2012年11月29日~2012年12月1日) - 第46回日本小児内分泌学会学術集会
(2012年9月27日~2012年9月29日) - 第35回日本分子生物学会年会
(2012年12月11日~2012年12月14日) - 第35回日本分子生物学会年会
(2012年12月11日~2012年12月14日) - Keystone Symposia : Emerging Topics in Immune System Plasticity
(2013年1月15日~2013年1月20日) - Keystone Symposia : Emerging Topics in Immune System Plasticity
(2013年1月15日~2013年1月20日) - 第35回日本分子生物学会年会
(2012年12月11日~2012年12月14日) - 第35回日本分子生物学会年会
(2012年12月11日~2012年12月14日) - 第35回日本分子生物学会年会
(2012年12月11日~2012年12月13日) - 第35回日本分子生物学会年会
(2012年12月11日~2012年12月14日) - 第35回日本分子生物学会年会
(2012年12月12日~2012年12月14日) - AACR Special Meeting; Tumor Invasion and Metastasis
(2013年1月20日~2013年1月23日) - 浜松ホトニクス 中央研究所 PETセンター
(2012年11月13日~2012年11月29日
(うち5日間)) - 54th ASH (American Society of Hematology) annual meeting
(2012年12月7日~2012年12月15日) - 54th ASH (American Society of Hematology) annual meeting
(2012年12月7日~2012年12月15日) - 54th ASH (American Society of Hematology) annual meeting
(2012年12月7日~2012年12月12日) - 33rd Annual San Antonio Breast Cancer Symposium
(2012年12月4日~2012年12月8日) - Society for Neuroscience 2012
(2012年10月13日~2012年10月18日) - Society for Neuroscience 2012
(2012年10月13日~2012年10月18日) - Society for Neuroscience 2012
(2012年10月13日~2012年10月17日) - Society for Neuroscience 2012
(2012年10月13日~2012年10月18日) - Stanford大学短期留学
(2012年8月20日~2012年9月16日) - BMAP 2012
(2012年8月29日~2012年8月31日) - BMAP 2012
(2012年8月29日~2012年8月31日) - BMAP 2012
(2012年8月29日~2012年8月31日) - BMAP 2012
(2012年8月29日~2012年8月31日) - BMAP 2012
(2012年8月29日~2012年8月31日) - Neuroscience 2012
(2012年9月18日~2012年9月20日(3日間)) - 浜松ホトニクス 中央研究所 PETセンター
(2012年7月24日~2012年8月8日(うち5日間)) - 第14回国際組織細胞化学会議(the 14th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry; ICHC 2012)
(2012年8月26日~2012年8月29日) - 共同研究施設訪問:University of Pittsburgh
(2012年9月23日~2012年9月27日) - 第71回日本癌学会学術総会
(2012年9月19日~2012年9月21日) - 第71回日本癌学会学術総会
(2012年9月19日~2012年9月21日) - EMBL Conference: Stem Cells in Cancer and Regenerative Medicine
(2012年8月29日~2012年9月1日) - ISEH (Society for Hematology and stem cells)
(2012年8月23日~2012年8月28日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012
(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012
(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012
(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012
(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012
(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012
(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012
(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012
(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012
(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012
(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012
(2012年6月14日~2012年6月15日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012
(2012年6月13日~2012年6月16日) - 10th International Society for Stem Cell Research 2012
(2012年6月13日~2012年6月16日) - The 58th/ 60th NIBB Conference
(2012年7月17日~2012年7月21日) - Cambridge大学ガードン研究所 留学記
(2011年4月28日~)
- 第35回日本分子生物学会年会
- 2011年度
- 2010年度
ホーム > Young Researchers' Trip report > Keystone Symposia : Emerging Topics in Immune System Plasticity
Keystone Symposia : Emerging Topics in Immune System Plasticity
氏名
柏木 一公
GCOE RA
微生物学免疫学教室
詳細
参加日:2013年1月15日~2013年1月20日
活動レポート
KEYSTONEという学会
The Plazaと呼ばれる広場を中央に据えた赤茶けた町では、どの建物も同じように見え、日本とはまるで異なるその様相は、私にとっての初めてのアメリカ、初めての海外学会を実感するには十分な佇まいをもっていました。ニューメキシコ州の州都サンタフェ。州都とは言っても人口6万人ほどの小さな町は1600年頃にスペイン人によって開かれたらしく、アメリカでも有数の歴史的な町とされています。
そんな小さな町で開かれたKeystone Symposiaと呼ばれる学会に参加させてもらいました。Keystone Symposiaは年に何度も開かれる生物学・医学分野における大小様々な学会の総称であり、今年で40周年を迎えるKeystone Symposiaの「Emerging Topics in Immune System Plasiticity」と題された今回の学会は、Keystone Symposiaに数ある免疫分野の学会の中でも特に免疫担当細胞の可塑性に着目した内容のものでした

初めての海外学会
先にも触れたように、私にとって今回のKeystone Symposiaは初めての海外学会であり、また初めてアメリカの地を踏む機会でもありました。日本とサンタフェとの時差は16時間、初めて経験する大きな時差はとても異様なもので、さらにサンタフェという町が海抜2000mほどの高地に位置しているため、環境の変化はとても大きいものでした。今回同行した吉村昭彦教授はこの環境の変化に体がなかなか順応せず、時差と高山病のようなもので最終日まで辛そうにしていましたが、私は高揚感がこれを打ち消し、帰国まで何の変調もきたしませんでした(帰国後にそのツケが全て回ってきて、2、3日は随分としんどい日々を過ごしましたが)。
大物ぞろいの学会
Keystone Symposiaは歴史ある学会で、一流どころの研究者たちが顔を揃えます。毎週のように(吉村研では論文が週に3回紹介されます)論文紹介で読まれるNature及びNature Immunologyなどの免疫学分野での超一流の雑誌、そのラストオーサーに名を連ねる大物たちを生で見ることができるということで、出発前からとても高揚した気分でした。生で見る大物は、案外と普通のおじさんたちでした。気さくで、目が合えば微笑みかけてくれる外国人たちに自然と緊張感はなくなり、とりあえず顔を覚えてもらおうと必死に話しかけてみたりもしました。
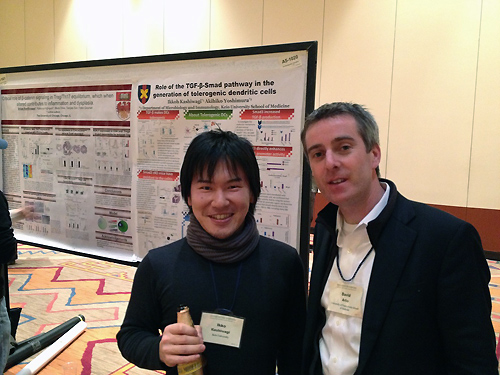
Keystone Symposiaという一体感
たった113人の参加者。今回の「Emerging Topics~」は例年になく少ない参加者であるとは聞いていましたが、私にはそうは感じられませんでした。超大物たちがいて、優秀な研究者たちがいて、そこに参加している人たち一人一人の存在感がとても大きく、たった113人とは到底思えない雰囲気がそこにはありました。さらに驚いたことに、今回の学会のタイムスケジュールはとても風変わりなものでした。まず午前7時、夜型の私は日本時間では到底起きる気配もない時刻に学会会場での朝食が始まります。近くにあるHiltonホテルがビュッフェ形式で用意してくれるものでした。そこで寝ぼけ眼を擦りながら学会参加者たちは朝の食卓を囲み、ホテルでの寝心地や天気の話、氷点下にまで下がる気温の話、気圧の変化による頭痛の話、そして前日やその日の演題の話に花を咲かせます。そうして頭も起きてきた午前8時に学会が開始され、11時過ぎまで午前の部が続きます。そして何と午後の部が始まるのは午後5時と、6時間もの休憩時間が設けられており、参加者たちは思い思いにその休憩時間を過ごすことができるのです。2日目、3日目には学会が企画してくれたスキーツアーがあり、さらに4日目には景勝地を訪れるバスツアーまで用意してくれていました。遠く離れたアメリカの地で、標高3000mはあろうかという高地のゲレンデでスキーを謳歌し、或いは崖の切り立った広大な土地に点在する先住民たちの居住区跡を見て回り、ホテルでシャワーを浴びたあと再び会場へ。そして午後の部の発表を聞き、午後7時、再びホテルが用意してくれたビュッフェを取りながら、参加者たちで食卓を囲んでの夕食が始まります。さらにその横の広いスペースにはポスターが張り出され、瓶ビールを片手にポスターを見て回るというとんでもなく自由な時間が流れていました。そんな空気に充てられて私もバドワイザー片手にポスターの前に立ち、少し回ったアルコールのおかげか苦手な英語も雄弁になり、参加者たちと闊達な議論を行うことができました。


海の向こうの研究者たち
活発なポスターセッションは毎晩夜の10時まで続き、朝7時から続いた1日の行程もようやく終わり研究者たちは会場を去ります。しかしそのままホテルに戻るはずはなく、1日を通して仲良くなった研究者同士、バーに繰り出してさらに酒を煽ることになるのは当然の流れです。スキーやポスターセッションで仲良くなった向こうのポスドクや大学院生と、初めてのアメリカのバーを経験し、注文の度に支払いをするその慣れないシステムに加え、ターン制を設けて「次は誰のおごりで」という訳のわからないノリを踏襲しながら、「Cheers(乾杯)!」を連呼したものです。しかし酒席で本音を言い合うのは国籍が違えど皆同じようで、酔ったアメリカ人たちと研究について、その心構え、現在の悩みやラボの様子など、色々な言葉を交わしました。海の向こう側でも、同じ苦労があり、同じ誇りがあり、そして同じような研究生活があるということ。その実態に触れたこと、そして研究に対して真摯で気概に満ちた同志たちとの触れ合いは、私の心に、ほんの少しではありますが確実に何かを芽生えさせました。

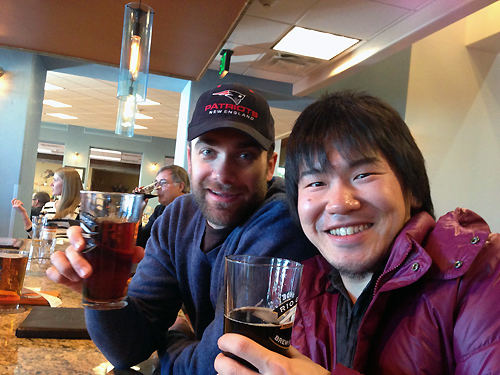
このような機会を与えていただき、日々厳しくも優しいご指導を賜っている吉村昭彦先生、そしてラボメンバーの方々にこの場をお借りして感謝の気持ちをお伝えするとともに、ご支援してくださったGCOE Young Researcher Support Plan、そして研究支援センターの担当者の方々に御礼申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。
Copyright © Keio University. All rights reserved.
