- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 骨髄由来の筋繊維芽細胞は間葉系幹細胞のニッチの構築と腫瘍増殖を促進する
(2011/03/25) - リプログラミングを促進する小さなRNA
(2011/03/25) - ⊿Np63は転写因子Lshを介して、がん幹細胞の増加を促す
(2011/03/25) - 造血幹細胞のメンテナンスを行う新たな因子の発見
(2011/03/04) - マウスES細胞から神経細胞への分化を方向づける因子の発見
(2011/03/04) - ヒト疾患iPS細胞:自閉症レット症候群への応用
(2011/02/18) - 生きかえる心臓
(2011/02/18) - グリオブラストーマ幹細胞様細胞は内皮細胞へ分化し、血管新生を誘導する
(2011/02/04) - 血液の幹細胞を保存状態と臨戦態勢に分類するNカドヘリン
(2011/02/04) - 急性骨髄性白血病のがん幹細胞への集中的治療を可能にするTIM-3
(2011/01/21) - p53の機能の回復を対象とした、がんの治療法には限界がある?
(2011/01/21) - 前立腺癌は分泌細胞、基底細胞のどちらに由来するのか?
(2011/01/07) - 癌細胞をリプログラミングする
(2011/01/07) - 造血幹細胞のエネルギー代謝や恒常性は、Lkb1によって調節される
(2010/12/24) - G-CSFによる造血幹細胞の末梢血への動員がEGFRシグナルの阻害により増強される
(2010/12/24) - 恐竜は何色?
(2010/12/10) - ヒト胚性幹細胞から軟骨細胞への分化誘導
(2010/12/10) - ヒト皮膚細胞から人工造血細胞への驚くべき変換
(2010/11/26) - ただ一つの遺伝子をヒトの皮膚細胞に導入し血液のもとになる細胞を作り出すことに成功
(2010/11/26) - TAp63のDicerを介した転移抑制機構
(2010/11/12) - ヒト細胞における、エンハンサー的機能をもつ長鎖ノンコーディングRNAの発見
(2010/11/12) - 毛包の前駆細胞から生じるSKPs(皮膚由来多能性前駆細胞)は、成人真皮幹細胞としての特性を示す
(2010/10/29) - X染色体上の遺伝子発現を正常化させると、体細胞クローン胚の生産効率は著しく向上する
(2010/10/29) - miR-9は乳癌においてE-cadherinの発現を抑制し、癌転移を促進する
(2010/10/15) - 間葉系幹細胞と造血幹細胞が形成する独特な骨髄ニッチ
(2010/10/15) - 細胞運命決定因子Musashiによる白血病の制御
(2010/10/01) - 単一のLgr5幹細胞からのin vitroでの陰窩・絨毛構造の構築
(2010/10/01) - 造血幹細胞は、インターフェロンγによって活性化される
(2010/09/17) - iPS細胞に残る由来細胞の記憶
(2010/09/17) - 生後の海馬の神経新生は、記憶(恐怖連合記憶)の情報処理(海馬依存的な期間)を制御する
(2010/09/03) - 核質に存在するヌクレオポリンは発生と細胞周期に関連する遺伝子の発現に直接的に関与している
(2010/09/03)
- 骨髄由来の筋繊維芽細胞は間葉系幹細胞のニッチの構築と腫瘍増殖を促進する
ホーム > 世界の幹細胞(関連)論文紹介 > 造血幹細胞のエネルギー代謝や恒常性は、Lkb1によって調節される
造血幹細胞のエネルギー代謝や恒常性は、Lkb1によって調節される
論文紹介著者
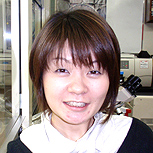
池尻 藍(博士課程 3年)
GCOE RA
微生物学・免疫学教室
第一著者名・掲載雑誌・号・掲載年月
Boyi Gan/Nature・vol 468・701-704・December 2010
文献の英文表記:著者名・論文の表題・雑誌名・巻・号・ページ・発行年(西暦)
Boyi Gan, Jian Hu, Shan Jiang, Yingchun Liu, Ergun Sahin, Li Zhuang, Eliot Fletcher-Sananikone, Simona Colla, Y. Alan Wang, Lynda Chin, Ronald A. Depinho. Lkb1 regulates quiescence and metabolic homeostasis of haematopoietic stem cells. Nature. 468:701-704,2010
論文解説
現在私は微生物学・免疫学教室において、酸素濃度の変化は細胞にどのような影響を与えるかについて研究しております。様々な細胞は酸素濃度の変化に応じて呼吸や代謝を変えてエネルギーを得ています。すなわち、細胞が生存や増殖する上で、酸素は非常に重要な因子の一つです。今回紹介させていただく論文では、細胞が存在している環境より受けるストレスに対して、いかなる方法でエネルギー代謝を行い、その恒常性を維持しているかについての新たな報告であったため、非常に興味を持ち取り上げさせていただくこととしました。
<研究の背景>
我々の体内を流れる血液は、赤血球や白血球、血小板などで構成されていますが、これらはもともと存在するのではなく、造血幹細胞と呼ばれる様々な血球系の細胞に分化することが可能な細胞より作りだされています。造血幹細胞は主に胸骨や肋骨、脊椎などの骨の中心部分である骨髄に存在し、近年の報告では、骨髄の中でも特に骨組織と骨髄の境界領域(造血幹細胞ニッチ)に高頻度に存在していることが明らかとなっています。この造血幹細胞ニッチの酸素濃度は、他の臓器や血液中と比較して低いことが知られており、ゆえに造血幹細胞のエネルギー代謝機構は、他の臓器に存在している細胞と異なると予想されますが、その詳細なメカニズムは未だ明らかにはなっていません。そこで著者らは、細胞内のエネルギーバランスの変化を感じるセンサーであるアデノシン一リン酸(AMP)活性化プロテインキナーゼ(AMPK)※1を調節する活性化因子であるLkb1に着目して、他の細胞と異なる環境下で、いかに造血幹細胞がエネルギーを作り出し、その機能を維持しているかについて解明しました。
<Lkb1を失ったマウスはどうなるのか?>
Lkb1の生体内での役割を知るために、骨髄や脾臓、胸腺などの組織特異的にLkb1を欠損させた成体マウスを作製したところ(Lkb1ノックアウトマウス ; Lkb1 KOマウス)、野生型のマウス(Lkb1 ワイルドタイプマウス ; Lkb1 WTマウス)と比較して、免疫細胞の分化、成熟の場である脾臓や、免疫細胞の中でもT細胞の分化の場である胸腺の重さの減少や骨髄中の細胞数の減少が見られ、急性の貧血を発症するなど重度の汎血球減少症※2を発症し、急激な体重減少の後に死亡しました。これは、Lkb1が欠損することで、造血幹細胞が様々な血球系細胞に分化する前段階の休止期から分化段階に移行できず、また分化した血球系細胞ではアポトーシス※3が亢進していることが原因であると示唆されました。
<Lkb1はどのように造血幹細胞の恒常性を維持しているのか?>
どのようにLkb1が造血幹細胞のエネルギー代謝や恒常性を維持しているのかを明らかにするため、Lkb1の働きを分子レベルで解析しました。詳細なメカニズムは省略しますが、Lkb1はmTOR複合体1(mTORC1)※4の活性化に関与することが知られています。そこで著者らは、まず造血幹細胞におけるLkb1とmTORC1の関係について調べましたが、Lkb1の欠損による造血に対する悪影響はmTORC1とは関係ありませんでした。しかしLkb1が存在しないことで、酸素呼吸の場として知られている細胞小器官であるミトコンドリアを活性化させるPGC-1の発現が減少し、ミトコンドリアの機能が低下することが明らかとなりました。
<まとめと感想>
著者らにより、造血幹細胞ニッチのような特異な場所に存在する造血幹細胞は、Lkb1によってミトコンドリアの活性を調節することで、エネルギー代謝や恒常性の維持を行っていることが解明されました。今後更なる研究が進むことで、造血幹細胞の機能が明らかとなるだけでなく、汎血球減少症に対する治療の開発に繋がることが期待されます。
用語解説
- ※1 アデノシン一リン酸(AMP)活性化プロテインキナーゼ(AMPK):
AMPで活性化されるタンパクリン酸化酵素。細胞内のエネルギーが欠乏することで活性化され、エネルギー産生経路の効率を高める。 - ※2 汎血球減少症:
血液中の赤血球、白血球、血小板の全てが減少している状態。原因としては造血幹細胞の減少、もしくは幼若な血球は作られるものの質的異常のために骨髄で破壊される、または末梢において血球を破壊する臓器である脾臓の腫大により、血球の寿命が来る前に破壊されることによる。 - ※3 アポトーシス:
多細胞生物の細胞で増殖抑制機構として管理・調節された能動的な細胞死。これに反してネクローシスは栄養不足、毒物、外傷などの外的環境要因による受動的な細胞死。 - ※4 mTOR複合体1(mTORC1):
細胞内や細胞外からのシグナルを統合し、細胞の代謝や増殖、分裂、生存を司る中心的な分子の複合体。mTORC1は免疫抑制剤の一つであるラパマイシンによって特異的に抑制される。
Copyright © Keio University. All rights reserved.
