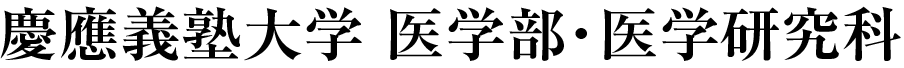腎臓の複雑さと美しさに魅せられて
2025/03/18
人口の高齢化に伴い、慢性腎臓病の患者数は増加の一途にあります。慢性腎臓病が進行して腎不全になると、透析や腎臓移植が必要になることは多くの人が知っていますが、実はそれだけではなく、脳卒中や心筋梗塞など心血管病のリスクを高めるほか、老化とも深い関係があることがわかってきています。今回は、腎臓内科学を専門とし診療や研究を行っている慶應義塾大学医学部内科学教室(腎臓・内分泌・代謝)の林香教授に、研究の動機や慶應義塾大学医学部で学ぶ意義等についてうかがいました。
臨床医としての知見を活かし、研究者として医学や医療の発展に貢献する
突然ですが、「フィジシャン・サイエンティスト」という言葉をご存知でしょうか。臨床医として患者さんを診察すると同時に研究者として自身の研究も行う、いわば医学界の二刀流。林教授はフィジシャン・サイエンティストであり、かつ学生を指導する大学教授でもあり、さらには一児の母という一面も。まさに一人四役の活躍ぶりです。
林教授が医学の道を目指したのは、小学校高学年の頃の経験がきっかけだそうです。
「祖母が胃癌を患ったときに診てくださった主治医の先生の、患者さん一人ひとりに真剣に向き合う姿に感動し、医師の仕事は責任が重いけれど、素晴らしい仕事だと強く印象に残りました」と林教授。その後、慶應義塾大学医学部に進学し学びを深める中で、「臨床医の仕事も人の命を預かる貴い仕事だけど、自分は研究も好きかもしれない」と気づいたそうです。
「未知のことを学び、自分の新しい世界が広がっていくことがすごく楽しいと思うようになっていきました。未知のことの中でも私が一番不思議だと思うのは、やはり生命のこと。とくに、人間の生命や体が一番神秘的でわからないことが多く、知りたいなという気持ちが強かったですね」
診療と研究の両方ができる環境は、「非常に恵まれている」と林教授。「臨床医ならではの視点やアイデアをベースとした基礎研究は、医療や医学の進歩にとって大変重要です。診療の質や研究の質も非常に高いレベルが求められていく中で、両方を専門にするのは非常に難しく課題も多いですが、やりがいも大きい」と語ります。
腎臓の複雑さと美しさに魅了され腎臓内科の専門医に
林教授の専門は、腎臓内科。なぜ腎臓内科を選んだのでしょうか。
「医学部を卒業すると2年間は初期研修医として、自分が選択した科で経験を積みます。私は、人間の命や身体を知る上で内科は重要だと思い、内科を選びました。初期研修が終わると自分の専門分野を選択し、専門医として修業を積みます。私は最初、神経内科の道に進もうと思っていたのですが、初期研修の最後の頃に腎臓の病理を学んだときに、腎臓の魅力に魅せられてしまいました」
腎臓には、糸球体という血液をろ過する装置がたくさんあります。糸球体でろ過された原尿は尿細管を通って最終的に集合管に達して、膀胱から体外に排泄されます。しかし、腎臓の働きはそれだけではありません。
「腎臓は多数の異なる細胞で成り立っていて、構造がとても複雑で、しかも美しい。
そして、単に尿をつくるだけでなく、身体の水分やミネラルのバランスを調整したり、血液をきれいにしたり、ホルモンを分泌したり、体のためにさまざまなはたらきをしている臓器です。その複雑さ、美しさ、全身の恒常性を管理している重要な臓器であるというところに非常に魅せられました。それで、腎臓内科を専門にしたいと思ったのです」
慢性腎臓病が進行するしくみと老化の関係を研究する
林教授が率いる研究チームが目下取り組んでいるのは、「慢性腎臓病と老化の関連性」を明らかにすることです。
「慢性腎臓病とは腎臓がだんだん悪くなる病気です。腎臓は“沈黙の臓器”といわれるとおり、疾患がかなり進行するまで症状が現れにくいという特徴があります。慢性腎臓病になるとやがて透析が必要になる、ということはみなさんご存知なのですが、慢性腎臓病の困ったところはそれだけではなく、何も症状が現れないうちから脳卒中や心筋梗塞など心血管合併症が起こりやすくなることなのです。また、慢性腎臓病があるだけで全死亡(がん、脳卒中、心臓病、その他すべての死亡の合計)率が高まると言われています」
さらに興味深いのは腎臓と老化の関係です。
「従来は、老化によって腎機能が低下し慢性腎臓病になると思われていましたが、実は腎臓が悪い人は老化が進んでいるということもわかってきました。つまり、慢性腎臓病が全身の老化を進める大きなファクターかもしれないのです。それはなぜなのかを研究でつきとめようとしています。これが解明できれば、腎臓病の治療だけでなく全身の老化やそれに伴って起きるさまざまな疾患についても、治療戦略の確立に寄与できるのではないか。そんな期待と興味を持って研究に取り組んでいます」
林教授の研究がユニークなところは、腎臓を構成する細胞のDNA損傷修復機能やエピゲノム(ゲノムに付加された情報)の変化に着目して、慢性腎臓病がどのように進行していくのかを明らかにしようとしている点です。
「DNA損傷やエピゲノム変化は老化と密接に関係しています。DNAは、ふだん私たちの身体の中で損傷と修復を繰り返しています。ところが身体が老化してくると、損傷したDNAが十分に修復されずに損傷が蓄積して、老化がさらに進んでいきます。
腎臓は、さまざまな細胞でできていて、どの細胞にDNA損傷が起きるかによって、その後身体に何が起こるかが全く違ってきます。たとえば、DNAのメチル化(一種の化学反応)が変化することで、免疫や代謝に異なる変化が起こり、合併症の程度も全く変わってくることが実験でわかってきました」
「腎臓が悪くなると、なぜ色々な合併症が起こったり老化が進んだりするのか。その謎を解く鍵を、このDNA損傷が握っているのではないか」
この仮説にたどりついたときはワクワクしたそうです。
林教授の研究成果によって、慢性腎臓病が治る病気になる可能性はあるのでしょうか。
「もし腎臓のDNA損傷と老化が関連する仕組みが解明されれば、治療戦略として考えられるのは、一つは腎臓疾患の症状の進行に関係する因子をブロックする治療法の開発です。もう一つは、検査などで腎臓病や老化のリスクの高い人を特定し早期治療を行うための指標とするという選択肢もあります。しかし、まだ研究は始まったばかり。先は長いです。全部一度に解決することは難しくても、ある一定の人には効果がある治療法を、私が現役のうちに見つけられるようがんばっていきたいです」
自分で手を動かして研究し、考えることが楽しい
多忙な日々を送る林教授。「研究はうまくいかないことのほうが多い」とか。それでも走り続ける原動力とは何なのかをうかがうと、すぐに答えが返ってきました。
「自分で手を動かして研究をすることが好きというのは一貫していますね。自分で仮説を立てて仮説通り新しいことを証明できたときもすごくうれしいですし、仮説とは違う結果が出てきたときに、『どうしてだろう』と考えてまた次に進んでいくというプロセスは本当に魅力的だと思っています」
今は、チームや組織全体を統括する立場なので、自分で手を動かして研究をする機会はなかなかないのが残念なのだとか。
それでも、「優秀な若手の先生たちと研究を進めていくことは刺激になりますし、育っていく姿を見るのも楽しいです。若手の先生たちが研究を好きになり、良いフィジシャン・サイエンティストになって、生き生きと活躍してくださるのが一番うれしいですね」
研究者や臨床医に向いているのはどんなタイプ?
林教授が大事にしていることは、学びへの好奇心を忘れないこと。
「医学や医療は日々進んでいるので、いつまでも勉強し続ける姿勢は大事だなと思っています。『半学半教』といって、『教員と学生も半分は教えて、半分は学び続ける存在である』という慶應義塾の精神があるのですが、その姿勢を持ち続けたいですね」
研究者や医師に向いているのはどんな人なのかも聞いてみました。
「研究者には、何か知りたいという気持ち、わからないことを明らかにしたいという気持ちが強い人が向いていると思います。また、研究って結果が出ないことも多いので、粘り強く、かつ楽観的な方がいいかもしれません。医師に向いているのは、患者さんと接する仕事ですので、人が好きな人のほうがいいでしょうね。それに加えて、しっかりと責任を持ってやっていく覚悟が必要だと思います」
仕事を選ぶときの極意についても林教授はご自身の体験も踏まえて答えてくれました。
「どの職業を選ぶにせよ、仕事は人生の中で長い時間を占めるので、自分が興味のあること、やりたいと思ったことを見つけること、そして最初の『やりたい』という気持ちをどれだけ長く持ち続けられるかも大事。長く情熱を傾けられるような仕事を見つけて、それにしっかり取り組んでいくと良いと思います。また、仕事は大事ではあるのですが、やはり自分が健康で幸せでなければ良い仕事はできないと思います」
慶應義塾大学医学部で学ぶ魅力
林教授は慶應義塾大学医学部を卒業し、その後も大学内で診療と研究を続けてこられましたが、慶應義塾大学医学部で学ぶ魅力は何なのでしょうか。
「まず、トップランナーの先生方が多く集まっていることが魅力の1つです。
次に、同級生が優秀で自分のやりたいことがはっきりしている方が多いこと。一緒に切磋琢磨しながらがんばる仲間がたくさんいることはとても幸せなことです」と林教授。
また、卒業後のキャリアについては、「多くの人は医学部を卒業したら医師として病院やクリニックで働くというイメージが強いと思いますがそれだけではありません。研究者になる人、研究成果を活かして起業する人、あるいは医者以外の仕事に就く人など、さまざまなキャリアパスがあります。もちろんフィジシャン・サイエンティストになる方もたくさんいます。慶應義塾大学は、学生の『これがやりたい』をサポートしてくれる懐の深い大学です」と強調します。
たとえば、慶應義塾大学関連スタートアップ制度やベンチャー・キャピタル、慶應義塾大学 信濃町リサーチ&インキュベーションセンターなど起業サポートの仕組みがあるほか、海外留学のプログラムも充実しているそうです。
「あらゆる角度から新しい医療や医学を牽引する人が育つ素地がある。それが慶應義塾大学医学部の最大の魅力だと思います」
林 香(はやし かおり)
慶應義塾大学医学部内科学教室(腎臓・内分泌・代謝)教授。
2004年、慶應義塾大学医学部卒業。国立国際医療センターにて初期研修を経て、2006年に慶應義塾大学医学部内科学教室入局。2007年~2011年に慶應義塾大学医学研究科博士課程にて学位取得(医学博士)。慶應義塾大学病院予防医療センター助教、腎臓内分泌代謝内科助教、同専任講師等を経て2023年より現職。
※所属・職名等は取材時のものです。