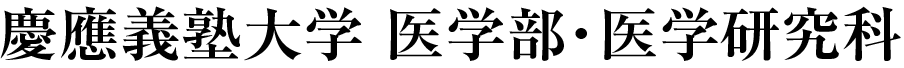目的
医学教育統轄センターは、慶應義塾大学医学部の教育目標である「独立自尊の気風を養い、豊かな人間性と深い知性を有し、確固たる倫理観に基づく判断力をもち、生涯にわたって研鑽を続け、医学と医療を通して人類の福祉に貢献する人材を育成する」ことを達成するための、教育体系の整備・運営・実践を行うとともに、広く日本医学教育界の発展に貢献することを目的としています。
組織
| センター長 | 門川 俊明 教授 |
|---|---|
| センター員 |
春田 淳志 教授 山口 慎太郎 准教授 堀 周太郎 専任講師 中島 理加 助教 鳥居 暁子 助教 フー, ユィーング 特任助教 |
センター事務長
| 兼務センター員 | 数名 |
|---|---|
| 事務職員 | 数名 |
沿革
| 2002年9月 | 医学部教授会 設置承認 |
|---|---|
| 2002年11月 |
医学教育統轄センター設置 初代センター長(兼任) 小口 芳久 教授(眼科学) 就任 |
| 2003年12月 | クリニカルシミュレーションラボ 開所 |
| 2004年4月 | センター長(専任) 天野 隆弘 助教授 就任 |
| 2004年8月 | PBLルーム 開所 |
| 2005年7月 | センター長(専任) 天野 隆弘 教授 就任 |
| 2009年4月 | センター長(兼任) 鹿島 晴雄 教授(精神・神経科学) 就任 |
| 2011年4月 | センター長(専任) 平形 道人 准教授 就任 |
| 2013年1月 | センター長(専任) 平形 道人 教授 就任 |
| 2017年10月 | センター長(専任) 門川 俊明 教授 就任 |
主な活動
慶應義塾大学の医学教育の中心的な組織
医学教育統轄センターは医学教育の最新の情報を集め、その中のIR部門によってデータの分析をおこない、カリキュラム開発への提言をおこなう、医学教育の中心的な組織です。医学教育の専門家が揃い、各教室で実践される医学教育のサポートを行います。医学教育統轄センター内には、IR部門が独立して組織されており、医学教育の実践とアウトカムをデータとして分析をおこなっています。
共用試験の実施・運営
共用試験評価実施機構による共用試験について対応しています。
-
CBT(Computer based testing)
臨床実習開始前の学生を対象とした、診療参加型臨床実習(クリニカル・クラークシップ)を行うにあたって必要な「知識」を確認する試験。
-
臨床実習前OSCE(Objective structured clinical examination)
臨床実習開始前の学生を対象とした、診療参加型臨床実習(クリニカル・クラークシップ)を行うにあたって必要な「知識・態度・技能」を確認する試験。
ファカルティー・ディベロップメント(FD)
医学教育に対する意識の向上・学生へのより良い教育の提供を目的として、教員を対象とした教育技法に関するFDセミナーを実施しています。さらには、優秀な教員を表彰する制度としてBest Teacher Awardと医学貢献賞を設けています。
-
Best Teacher Award
2006年、医学部におけるファカルティディベロップメントと教育水準の向上を目的として、「Best Teacher Award」を設立しました。毎年、学生による授業に関するアンケート調査の結果にもとづき、学年毎にBest Teacher が選出され表彰されます。
前年度の結果については、以下をご参照ください。
-
医学教育貢献賞(Outstanding teacher award)
医学教育貢献賞は、Best Teacher Awardの第1位を3回以上受賞した教員に贈られる賞で、2019年度より新設されました。
医学教育貢献賞を受賞した教員は、翌年度以降のBest Teacher Award選出対象からは外れますが、今後の医学教育を担う若手教員に対する模範として活躍することが期待されています。
トレーニングセンターの運営
-
クリニカルシミュレーションラボの運営
信濃町キャンパス所属の学生・研修医・看護師を対象とし、種々のトレーニングモデルを用いた医療に関する技能の修得を行っています。2023年には東校舎の第1クリニカル・シミュレーション・ラボに加えて、2号館10階の第2クリニカル・シミュレーション・ラボが設置されました。専従の管理者が管理をおこなっています。
-
クリニカルアナトミーラボ(CAL)の運営
解剖で得られた成果を医学および社会に還元し、医学、医療の発展に大きく貢献するために、医師に対して技術の習得を含めた高度の解剖学教育と優れた解剖研究を行う施設です。
医療者教育研究
医学教育統轄センターでは、医療者教育に関連する研究を行っています。
匿名化された成績、アンケート、観察データなどの情報のみを用いて行う教育研究については、国が定めた倫理指針に基づき必ずしも対象となるお一人ずつから直接同意を得るとはかぎりませんが、研究の目的を含めて、研究の実施についての情報を通知又は公開し、さらに可能な限り拒否の機会を保障することが必要とされています。このような手法を「オプトアウト」といいます。
研究のために自分のデータが使用されることを望まれない方は、各研究の担当者までお知らせください。