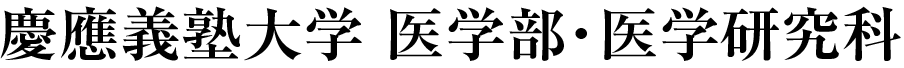ヒトはなぜ
研究をするのでしょうか?
医学研究科委員長 佐藤 俊朗
慶應義塾大学大学院医学研究科で研究をする意味について、私自身の考えをお伝えしたいと思います。まず「研究とは何か?」という問いから始めたいと思います。深遠なテーマですが、ここでは「新しい知識を切り拓く行為」と定義します。つまり、教科書に載っている知識を少し広げたり、あるいはこれまで誰も知らなかった知識をつくり出したりする営みです。
慶應義塾大学大学院医学研究科での研究には、大きく分けて二つの方向性があります。一つは「出口研究」。病気の診断や治療、予防など、最初から明確なゴールがある研究です。医療に直結し、社会からの期待も大きい分野といえるでしょう。もう一つは「入口研究」。こちらは、なぜ病気が起こるのか、生命はどのように成り立っているのかといった純粋な好奇心から始まる研究です。すぐに治療に結びつかないこともありますが、根源的な問いに挑むことで新しい視点や未来の可能性が広がります。実際には、研究は単純に入口と出口に分けられるものではありません。出口研究を進める中で入口の問いに直面したり、好奇心から始めた研究が思いがけず治療法の発見につながったりします。その行き来の中にこそ、研究の醍醐味があります。
では「なぜ研究をするのか?」と問われたとき、私が一番しっくりくる答えは「面白いから」です。思い通りに進まず苦しい時期もありますが、試行錯誤を経て意外な発見に出会えたときの驚きと喜びは格別です。研究の「面白さ」とは、予想を裏切る結果や、社会に大きく役立つ可能性を秘めた瞬間に宿るものだと思います。
これから研究を進めていく皆さんには、ぜひその「面白さ」を自分の手で味わってほしいと思います。困難を乗り越え、自分だけの新しい発見を形にしたときに得られる達成感は、きっと一生の財産になります。慶應義塾大学大学院医学研究科という場が、皆さんの挑戦を支え、夢を実現する舞台となることを心から願っています。

慶應義塾大学大学院医学研究科委員長、医化学教室教授。主な研究領域は、消化器病学、腫瘍学、分子遺伝学、再生医学、幹細胞生物学、生化学。
関連コンテンツ