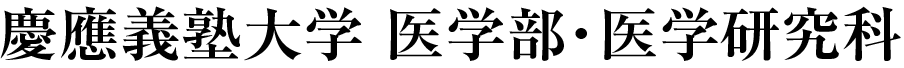最後の知的フロンティア「脳」の解明を目指して
2024/01/29

なぜ治るのか そのメカニズムを知りたくて
「なんとなく『心』に興味があったから」と意外にもふわりとした理由で、慶應義塾大学医学部の精神・神経科学教室に入ることを決めたという田中謙二教授。研究にのめり込むきっかけになったのが、研修医として初めて精神疾患の患者を目の当たりにした際の衝撃だったといいます。
「精神疾患というのは人をこんなにも悲惨な状態にしてしまうのか……と驚きました。そしてそれ以上に、薬物治療で劇的に症状が良くなっていくことに大変な衝撃を受けました。しかも、その薬がなぜ効くのかについては、教科書を手当たり次第読んでもさっぱりわからない。いわばブラックボックス状態にある『回復のメカニズム』を解き明かしたいと思いました。」
大学院は、神経化学の大家である植村慶一名誉教授率いる生理学教室へ。その後、藤田医科大学総合医科学研究所や生理学研究所で研鑽を積みました。
「当時、つまり2000年の初め頃は、神経の遺伝性疾患の遺伝子が次々に同定されていった時代。神経細胞についてどんどん明らかになっていくなか、それ以外のグリア細胞については機能もよくわからないし、注目する人もそれほどいなかった。こっちを研究すれば何かわかるのではという“思い込み”で研究を始めました。生理学研究所の池中一裕教授は鷹揚な方で、『グリア研究で精神疾患がわかるのか俺は知らんが、やりたいならやってみなさい』と温かく後押ししてくださいましたね。」
「ほぼ無知だった医学生」が精神・神経科学教室の門を叩いてから、およそ四半世紀。田中教授はいま、30名以上の研究者・医学生が集う先端医科学研究所脳科学研究部門を率いています。
「患者の状態が良くなる、以前はできなかったことができるようになる。そういうダイナミックな変化を生み出す脳基盤は何なのか、ずっと追いかけてきました。先端医科学研究所脳科学研究部門が目指すのも、脳の機能や脳の機能障害を改善させる方法を知ることです。それは同時に、『ヒト脳とは何か』という大きな問いと向き合うことでもあります。」
脳科学研究を一変させた、革新的な新技術
数百億個の細胞から構成され、一つの細胞が1万以上の入力を受け取るといわれる脳。この途方もなく複雑な脳の「構造」や「機能」の解明は、テクノロジーの進化とともに一歩ずつ進んできました。
たとえば、1970~1980年代に病院へ導入された「CT(コンピューター断層撮影法)」や、「MRI(磁気共鳴画像法)」は、生体内部の情報の可視化を実現。また、1990年代から普及した「緑色蛍光タンパク質(GFP)」は、細胞の活動を維持させたまま光学顕微鏡で観察することを可能にしました。さらに2009年には、個々の細胞から遺伝子発現を調べることができる技術「シングルセルバイオロジー」が出現。細胞の分類や状態の知見が深まり、脳の「構造」の解明は大きく前進しました。
しかし、「問題は、脳の『機能』を明らかにすることでした」と田中教授。
「特定の神経活動と行動の因果関係を突き止めることは、極めて困難でした。動物実験においても、電気刺激では広範囲に刺激が伝わってしまい、特定の神経細胞だけを操作することはできません。直接証明する方法がないわけですから、神経細胞の活動と行動の関係は従来、相関関係に基づく推測の域を出ませんでした。たとえば、大脳基底核を構成する線条体に存在する2種類の投射神経については『ドパミン受容体1型は運動を促進する“だろう”』『ドパミン受容体2型は運動を抑制する“だろう” 』ということまでしか言えなかったのです。」
そこに大きな変革をもたらしたのが、2005年に登場した「オプトジェネティクス(光遺伝学)」です。
「オプトジェネティクスは、光照射のオンオフによって、機能を知りたい細胞の活動をミリ秒単位で精緻に操作する技術です。体内で細胞の活動を操作でき、時間・空間の正確性も高い。神経活動と行動の関係を初めて因果関係で実証できるようになり、以後、神経細胞の『機能』の解明が一気に進みました。」
実は、この画期的な技術の黎明期に、田中教授が関わっていたのだそうです。
「2006年に私はコロンビア大学に留学し、レネ・ヘン教授のラボに在籍していたのですが、彼のもとではオプトジェネティクスを開発したカール・ダイセロスがしばしば訪ねてきました。『新しい技術ができたから試してみてよ』と本人がラボにやって来るのですが、当初は培養細胞にしか使えない未熟なものでした。トライ&エラーを繰り返して、マウス個体で使えるようになるまでに数年費やしました。優れた技術をより広く使いやすいものにしていく過程に携われたことはうれしいですね。オプトジェネティクスはいまや、脳科学研究に不可欠な技術であり、神経細胞のみならずグリア細胞や血管細胞の操作にも活用されています。」

「意欲」の神経基盤を解明 うつ病の治療にも期待
ヒト脳の全容を解明し、脳の“地図”を描こう──。そんな野心的な巨大研究プロジェクトがいま、世界各国で進められています。2013年から始まった米国のBRAIN Initiative、欧州のHuman Brain Projectに続き、日本でも2014年から「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト(革新脳)」がスタート。
「世界中の天才的な研究者が懸命に探索してもなお、脳には未知の領域がまだまだ残っている。自分もそこにチャレンジできるというのは、非常にやりがいがありますし、ありがたいことだなと思います。」
そんな田中教授らの近年の研究成果の一つが、「意欲」に関する研究です。
「うつ病や認知症、脳血管障害などでは、意欲の低下が高頻度で見られます。一方で依存症では、異常な意欲の亢進が見られます。このような意欲障害をもたらす神経基盤はほとんどわかっておらず、とくに脳損傷後の意欲低下に対して治療法は全くないのが現状です。」
田中教授らの研究グループは、脳損傷や脳変性疾患の意欲低下症例を参考に、脳深部にある「腹外側線条体」の構成要素である「ドパミン受容体2型陽性中型有棘ニューロン(D2-MSN)」に注目。このD2-MSNが徐々に死んでいく遺伝子改変マウスを作成し、脳変性疾患を模倣しました。まずマウスに「レバーを押せば押すほどエサがもらえる」ことを学習させました。レバーをより多く押すマウスが、意欲行動をより多く行い、意欲が高いと解釈します。十分に意欲的であったマウスが、腹外側線条体のわずか17%の細胞死で意欲が減退することが判明。さらにオプトジェネティクスによる D2-MSN の機能抑制によって、腹外側線条体の D2-MSNが意欲行動の開始に必須であることが明らかに。意欲行動の開始を担う神経、「さあ、やるぞ!」を担当する神経、いわば“やる気ニューロン”の存在を発見した論文は、2017年、『Nature Communications』に掲載されました。
続く2019年には、意欲行動を持続させる「根気」に注目した研究を発表。意欲行動中の「腹側海馬」は、セロトニンによって神経活動が低下すること、また、腹側海馬神経細胞の活動抑制が意欲行動の持続に必須であることを明らかにしました。
「『さあやるぞ』という意欲行動の開始と、『最後までやり切る』という意欲行動の継続は、それぞれ異なる脳領域・神経細胞によって制御されていることがわかりました。さらに、腹内側線条体の神経細胞が活性化すると、目標行動を抑制する無駄な行動が増えることもわかっており、こちらは “移り気ニューロン”として研究を進めています。『やる気』『根気』『浮気』の神経基盤の解明は、意欲の低下・上昇のメカニズムの理解や治療法の開発、さらに柔軟性に欠ける適応障害や強迫性障害などの病態の理解につながっていくと考えられます。」
「構造」の異常から、ヒト疾患の解明を目指す
近年は、ヒトやマウスのMRI脳画像から脳構造の異常を解析するという新たなアプローチにも注目が集まっているといいます。
「健常者と精神疾患患者の違いとは、脳の『機能』の違いであり、それは脳の『構造・形』に現れるという考えに基づくものです。たとえば、覚醒剤依存になっている状態とそうでない状態では脳のどこが違うのか。うつ病患者が抗うつ薬で症状が良くなるときに脳のどこが変わっているのか。実験動物に限った話しですが、これらをMRIや電子顕微鏡で調べると、それぞれ『帯状回』『腹側淡蒼球』に変化が起こっていることがわかっています。」
2023年に田中教授らが発表した、パーキンソン病の薬剤副作用のジスキネジア(運動異常)が進展するメカニズムも、脳の「構造」の変化を捉えたことが突破口となりました。
パーキンソン病患者が治療薬L-DOPAを長期間服用することで、体・手足のくねくねした動きを発症する難治の副作用、L-DOPA誘発性ジスキネジア(LID)。一方、精神疾患患者も、抗精神病薬を長期間服用することで、遅発性ジスキネジア(TD)という口のもごもごした動きを発症することがあります。
「異なる疾患に異なる薬剤を用いているにもかかわらず、よく似た副作用が生じることから、私たちはLIDとTDの発症には共通するメカニズムが存在するのではないかという仮説を立てました。」
そこで、LIDモデルマウスとTDモデルマウスを作成し、共通する脳構造異常を探索したところ、いずれの病態においても、線条体神経細胞の軸索末端と淡蒼球神経細胞体が肥大することを発見。その後、線条体神経の「VGAT遺伝子」の発現増加がジスキネジア発症につながる要因であることを解明し、さらに脳内ドパミン濃度が変動することがVGATの過剰発現をもたらすことも明らかにしました。
「この研究は、大脳基底核の細胞の肥大という『構造の変化』に気づけたことが、遺伝子の同定、機能の解明につながりました。今後、蓄積されたヒト脳データを活用したこうしたアプローチもまた、ヒト疾患のさらなる理解へとつながっていくと期待しています。」

懸命に、愚直に、試行錯誤する研究者であれ
研究のかたわら、週に1回は精神・神経科の外来に出ているという田中教授。
「研究者というのは『解けそうな問題』に目が向きがちですが、そうではなく、『本当に困っている問題』の解決に資する研究をしようという思いに引き戻してくれるのは、やはり目の前の患者さんです。」
では、脳科学の研究者に向いている資質などはあるのでしょうか。
「脳科学の領域に限った話ではないと思いますが、絶対にこうなるはずと決めてかかる人は、あまり向いていないかもしれません。仮説通りに進んでも楽しいですが、むしろ仮説通りに進まない時の試行錯誤に面白さを感じられること。どんな結果も受け入れて丁寧に解釈し、何度でも繰り返し実験に向き合えること。そんな姿勢が大切だと思います。」
とはいえ、どんなに試行錯誤しても打開できない困難な状況に陥ることも少なくないのでは。
「うまくいかなかったりほかの研究者に先を越されたりすることは、もちろん多々ありますが、気にしません。手を動かしてデータを取っている者だけがその過程で得ているものは必ずあるからです。それに、いまは仮説通りにいかず失敗だと思っていた研究結果も、ずっと後になって『実はアレって大事なことだったのか』と気づくこともあります。」
ところで、若かりし頃の田中教授が“思い込み”で始めたというグリア研究のその後の進展については、「国内外で研究が進み、グリア細胞の多くの重要な働きがわかってきたが、20数年経っても疾患の理解にはほど遠い」とのこと。それでも2021年には田中教授らが、グリア細胞の一つ、オリゴデンドロサイトに発現する特定の分子が年齢に依存する神経可塑性を制御できることを発見。加齢などで低下した脳機能の改善に貢献することが期待されており、その研究はいまも地道に続けられています。
厳しくも楽しい そんな仕事に出会ってほしい
前身の研究室から12年にわたって、出身校も国籍も多彩な研究者らとともにさまざまな研究成果を上げてきた先端医科学研究所脳科学研究部門。ラボには、田中教授が長年掲げている3つのモットーがあります。それは、「Beauty is truth」、「研究を楽しむ」、そして「共同研究者から学ぶ」。
「『Beauty is truth』は、生理学研究所の濱清名誉教授が信条としていたものを受け継がせていただきました。顕微鏡で見る細胞の配置や形は、本当に精緻で美しいものです。面白いのは、遺伝子を改変したりオプトジェネティクスで細胞の活動を操作したりすると、その綺麗な形が崩れることがあるのです。美しいものには理由があり、美しさの中に真実がある。この感覚に共感する研究者は割と多いと思います。」
二つ目の「研究を楽しむ」もまた、亡き恩師、池中一裕先生の姿勢から学んだものだそうです。
「池中先生は本当に自由に楽しく研究をされる方で、そのおかげで私も研究者を続けられたと思っています。どんな業界・職種においても、楽しんで仕事をしていらっしゃる人ってやっぱり幸せそうですよね。若い皆さんも大いに楽しみながら、医学・医療に打ち込んでほしい。これに尽きます。もちろん楽しさの裏には、厳しさや苦しさも伴いますが、諦めずにやり切ることです。」
三つ目の「共同研究者から学ぶ」には、損得ではなく、互いの技術・知識を交換し互いを高めるために共同研究をしようというメッセージが込められています。これは教員と学生の関係における「半学半教」にも通じるものだといいます。
最後に、これから医学・医療の道を志す若い世代にメッセージをいただきました。
「自分が何に向いているのかわからないという声をよく聞きますが、そんな人には『いろいろなことをつまみ食いしてみれば』『とりあえずやってみたら』とアドバイスしています。それが脳科学研究ならもちろん私たちは歓迎します。とにかく、学生の間にたくさん自分探しをやってみればいいと思いますよ。心から楽しいと思える道を見つけて頑張ってほしいと思います。」

田中 謙二(たなか けんじ)
1997年、慶應義塾大学医学部卒業。2003年、慶應義塾大学大学院医学研究科博士課程修了。生理学研究所のポスドク・助手、コロンビア大学留学を経て、2008年、生理学研究所助教に。慶應義塾大学医学部精神・神経科学特任准教授・准教授を経て、2021年から現職。NARSAD Young Investigator Awards、三四会奨励賞、神経化学会優秀賞、野村達次賞、北里賞など受賞歴多数。
※所属・職名等は取材時のものです。