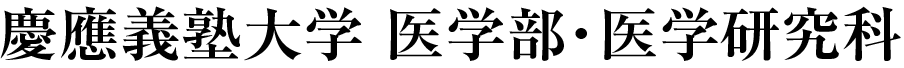ロボット手術に薬物治療 奥深い泌尿器科の世界へようこそ
2023/09/29

「小さな科なのに全部やる」 その独自性に惹かれて
医学生時代、「泌尿器科だけ世界が違う」と感じたという大家教授。
「臨床実習でいろいろな診療科を回りましたが、泌尿器科の充実度には驚かされました。まず、泌尿器科は、診断も手術も薬物治療も全部やる。たとえば胃がんや肺がんであれば、診断は内科で、手術は外科で、薬の治療はまた内科に戻す、といったやり方が普通ですが、泌尿器科はそういった分断がなく、患者の全部を診るんです。しかも、腎臓移植のような本格的な手術もやるし、高度な薬物治療もする。基礎研究をはじめとする研究環境も整っている。小さな科なのにすごい所だなと思いました。」
泌尿器科学教室の独特の雰囲気にも、心惹かれるものがあったといいます。
「ステレオタイプの価値観に縛られない、自由な雰囲気でした。若い先生も上の先生に平気で物を言うし、まさに『半学半教』を地で行っていたという印象ですね。また、1980年代当時にしては珍しく、グローバルな視点を持っている人が多く、海外での研究や学会の話もよく話題にされていました。何より、当時の泌尿器科学教室を率いていた田崎寛教授は、絵を描くのがご趣味で芸術家肌というか、診療も研究も発想がまるで人と違っていた。この人についていきたい、と思わせる人間的魅力のある方でした。」
ここなら人が少ない分、目をかけてもらえるだろうし、一生懸命やればいつか一人前になれるだろう。そう確信した大家教授は、迷わず泌尿器科に入局。「慶應に入ったことと泌尿器科を選んだことは、これまでの僕の人生において最も良い選択だったと思います。そのほかの選択ではいろいろと失敗していますが(笑)。」
泌尿器科の世界は「アリス・イン・ワンダーランド」
1+3の「1」は、悪性疾患。腎がん・膀胱がん・前立腺がんの泌尿器3大がんや、精巣がん、副腎がん、後腹膜腫瘍などです。1+3の「3」は、多岐にわたる良性疾患をⅠ〜Ⅲの3つの領域に集約したもの。[領域Ⅰ]は腎臓・透析医学で、腎移植も扱います。[領域Ⅱ]は内分泌代謝学・神経泌尿器科学で、副腎疾患や前立腺肥大症、神経因性膀胱、排尿機能障害などに対応します。そして[領域Ⅲ]が生殖医学・アンドロロジー。男性不妊や性機能障害などを扱います。
「たとえば前立腺がんの手術をすると、合併症として、排尿障害やEDを引き起こすことがよくあります。ところが、がんの手術自体はできても良性疾患には対応できないという病院も多いのです。多様な領域を診られるよう体制を整えてきた慶應では、『1』でがんの手術を行った後も、排尿障害が起これば『3』の[領域Ⅱ]の、EDの症状が見られれば[領域Ⅲ]の専門の医師が対応できます。日本には80以上の大学病院がありますが、泌尿器疾患のほぼすべてを網羅できる病院は、いまのところ慶應以外にありません。」
さらに2009年からは、泌尿器科医のなかでも数少ない「小児泌尿器科」専門のチームを発足。先天性水腎症、膀胱尿管逆流症、尿道下裂、停留精巣などさまざまな小児疾患の対応が可能になり、いまでは年間150以上の手術を実施しています。「小児泌尿器科での手術手技を成人の治療に応用した事例もありますし、再建手術のスキルを若手が習得する場にもなります。」
「1+3構造」の幅広い泌尿器疾患を網羅し、各領域が有機的に連携することが、質の高い医療・研究・教育につながっている、と大家教授。
「泌尿器科は小さな科で、その入り口こそ狭く見えるけれど、ひとたび中に入ってみると、その先に広がっている世界は驚くほど奥深くてエキサイティング。僕はいつも、泌尿器科はまるで『アリス・イン・ワンダーランド』のような世界だなと思っているんです。」
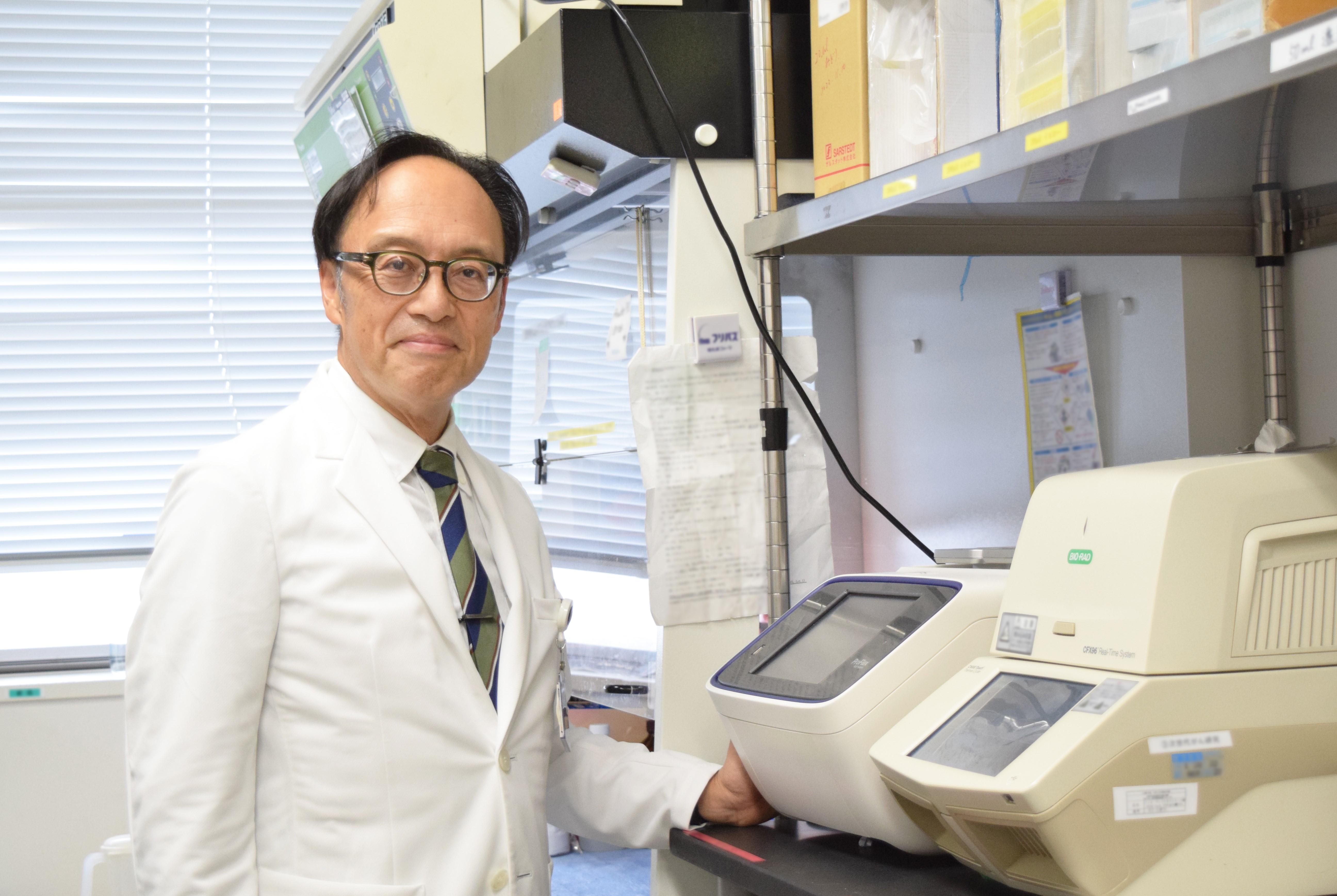
2000年代に飛躍的な進歩 ロボット手術に複合免疫療法も
大家教授が泌尿器科学の道を歩んで36年。「医者になった頃は、将来の泌尿器科治療がこれほどガラッと変わるとは思わなかった」との言葉通り、ここ20年ほどの間に、泌尿器疾患の治療にはさまざまなパラダイムシフトが起こっています。
その一例が、「ロボット支援手術」です。2012年、ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘出術が日本で初めて保険適用となり、その後も副腎摘除術、腎部分切除術・腎摘術、膀胱全摘除術、腎盂形成術、仙骨膣固定術など、多くの術式が保険収載されました。
「ロボット支援手術は、より繊細で正確な手術操作が可能になるため、出血量が極端に少ない、傷口が小さく目立たない、術後の回復が早いなどのメリットがあります。今日では、前立腺がんに対する手術はほぼすべてがロボット支援手術で行われており、腎がんや膀胱がんも腹腔鏡手術かロボット支援手術が中心です。2018年以降、ロボット支援手術は外科領域にも徐々に拡張されていきましたが、その技術力をリードしてきたのは間違いなく泌尿器科であるといえるでしょう。」
「薬物治療」においても、その標準治療は目まぐるしく変わってきました。たとえば腎がんの場合、以前主流だったのは「サイトカイン療法」。「これは、免疫細胞が産生するタンパク質のインターフェロンやインターロイキンを投与して免疫細胞の働きを活性化し、がん細胞を攻撃しようというもの。この治療も画期的ではあったのですが、奏功率は15%程度とかなり低いものでした。」
状況が大きく進展したのは、2008年のこと。「腫瘍血管新生をターゲットにした『分子標的治療』が取り入れられるようになり、患者さんの予後は驚くほど変わりました。これは、腫瘍細胞や血管内皮細胞の増殖にかかわる細胞内シグナル伝達を、チロシンキナーゼ阻害剤やmTOR阻害剤で阻害することによって、腫瘍の増殖を抑えるという治療です。当時、緊急入院で運ばれてきた患者さんに、承認されたばかりのスニチニブを投与したのですが、15年経ったいまもご存命です。インターフェロンの時代であればこうはいかなかったでしょう。」
さらに2016年には、がん細胞が免疫を逃れて生き延びようとする機構をブロックする「免疫チェックポイント阻害薬」が保険適用に。投与すると効果が長く持続することも確認され、治療の選択肢が広がっていきました。
そして2018年。「新たな時代が始まった」といわれるほど泌尿器科治療に大きなインパクトを与えたのが、「複合免疫療法」の登場でした。「複合免疫療法とは、2種の免疫チェックポイント阻害薬(PD-1/PD-L1阻害薬とCTLA-4 阻害薬)、あるいは、分子標的薬(VEGF阻害薬)と免疫チェックポイント阻害薬(PD-1/PD-L1阻害薬)をコンビネーションで投与する治療です。現在は薬剤の組み合わせによって5つの選択肢があり、患者さんの状態や希望によって使い分けています。」
分子標的治療薬単体の時と比べて、18カ月生存率が予後中間群では約1.5倍に、予後不良群では2〜3倍に延長したというデータも発表されている複合免疫療法。「 すでに想像以上の進歩を遂げていますが、さらなる効果を発揮する新たなコンビネーションを探るべく、いまも世界中で治験が進められているところです。」
日進月歩のがん治療も、克服すべき課題は山積
立ちはだかる難題の一つが「治療抵抗性のがん」、すなわち、治療が効かない、あるいは、治療を続けるうちにその効果が減弱していくがんにどう対処するか、という点です。
「たとえば、腎がんの複合免疫療法の奏功率がいまは高い人でも、いずれその効果が下がる時が来ます。がん細胞というのは姿・形をたくみに変えて生き延びようとするしたたかな連中ですから。その薬剤抵抗性のメカニズムを解明し、新たな治療法を探る研究が国内外で進んでいます。」
たとえば、前立腺がんの場合。治療を続けていくと、去勢抵抗性前立腺がんの一部は、神経内分泌がんの形質を持った、より難治性の前立腺小細胞がんへと変異することがあります。そして前立腺小細胞がんでは、がん抑制遺伝子のp53とpRBに変異が見られることがわかっています。
「僕らは、このがん幹細胞性・治療耐性への進展プロセスと、体細胞からの多能性幹細胞性獲得プロセス(iPS細胞誘導)が類似していることに注目。山中因子の一つ、OCT4の発現が高い細胞群で抗がん剤耐性化が進んでいることを突き止め、既存の抗がん剤と併用して効果の出る薬剤を見出すと、2015年には臨床試験に世界で初めて成功しました。抗がん剤が効きにくくなったがんに再び抗がん剤が効くようにする、すなわち、抗がん剤の感受性を巻き戻すという『リプログラミング療法』の研究に注力して約10年、今後も着実に研究を重ね、新たな治療へとつなげていくつもりです。」
膀胱がんの治療にも、課題があります。
「膀胱がんの治療には、TURBT(経尿道的膀胱腫瘍切除術)や、BCG(ウシ型弱毒結核菌)などを注入する膀胱内注入療法があります。ただし、膀胱がんは複数の箇所に多中心性に発生し、再発を繰り返すのが特徴。そしてがんが筋層まで浸潤すると、原則として膀胱全摘をしなければなりません。侵襲が高くアピアランスも変わってしまう膀胱全摘は、できることなら避けたい。そのためにも、BCG抵抗性の筋層非浸潤性膀胱がんの治療法を見つけるべく、研究を続けています。」
「現状に満足することなく、アンメット・メディカル・ニーズに果敢にアプローチしていく。僕ら一人ひとりのそうした姿勢が、これからの泌尿器科学を転換・進展させていく力になると思っています。」

診察室の去り際まで気にかける、その理由
医師・研究者として、そして教育者として、多忙な日々を送る大家教授。どんな時も大切にしているのは、最大限の努力を重ね、そして「全力で目の前の相手と向き合う」ということ。
「外来の際、僕は患者さんが診察室を出ていくときの表情まで注意深く見ています。物足りなさそうな様子であれば、『後でもよければ、もう一度時間を取りましょうか』と声をかける。医者ができる限りの対処をし、きちんと向き合って話をすれば、たとえどんなに厳しい状況であっても、患者さんは納得し満足してくれます。医学・医療というのはヒューマニズムに根ざしているものですから、医者は常に患者さんの気持ちを推し量りながら、バックグラウンドや性格まで考慮したうえで話をするべきなんです。患者さんに対して、どんなに丁寧に接しても丁寧すぎるということはない。このことを、僕は慶應の泌尿器科学教室の先生方の背中を見て学び盗んできました。若い先生方にも、僕の姿を見て何かを感じ取ってもらいたいですね。」
大学の講義や学会の場でも、大家教授のモットーは変わりません。
「入学したての1年生対象の『医学概論』という授業があるのですが、僕は『君たち、今日はありがとうっ!これから本気モードで授業やで!』と始めるもんですから、教室は大盛り上がり、拍手喝采です。授業が終わると『楽しかった!』と学生が寄ってきますよ。学会発表でも、僕は演台に立ったら聴衆とのアイコンタクトから始めます。めっちゃ変な人きたわ、と興味を持ってもらえたらこっちの勝ちです(笑)。授業も講演も、イヤイヤやったところで相手には何も伝わりません。万全の準備をして臨み、目の前の人のために全力を尽くす。それが一番大事なんだと思います。」
生まれ変わっても、また泌尿器科医になる
数ある診療科のなかでも、「マイナーな科」とのイメージが強い日本の泌尿器科。一方、海外では泌尿器科の人気は非常に高く、少数精鋭の「狭き門」の一つなのだそうです。
「UCSF(カリフォルニア大学サンフランシスコ校)の泌尿器科で活躍されている篠原克人先生は以前、UCSFの泌尿器科は、3人の枠に毎年300人の応募が来るとお話しされていました。僕が留学していたドイツのデュッセルドルフ大学でも人気は高く、学生時代から出入りしないと泌尿器科には入局できないほどでした。」
泌尿器科が支持を集める理由を、大家教授は次のように分析します。
「診断から薬物治療、手術、さらに術後の全身管理までのすべてを担当するという、仕事のやりがいや面白さがやはり大きいのだと思います。医師として背負う責任も、そこで得られる満足感も半端ないですから。さらに、泌尿器疾患は緊急手術が少なく、術後の合併症も起こりにくいので、医師のQOLも保たれます。実際、最も離局率が低い診療科という調査もあります。一度入ったらやめる人が少ないんですね。ちなみに、いま慶應のキャンパスに貼ってある泌尿器科の宣伝ポスターには、『私たちは生まれ変わっても泌尿器科医になる』と謳われているんですが、まさしくその通りだなと思いますね。」
そして最近、「この泌尿器科の素晴らしい世界が、日本でも少しずつバレてきたんです(笑)」と大家教授。
「今年の泌尿器科学教室には7人も入局しました。泌尿器科はロボット支援手術で他の科をはるかに先行していますから、『ロボット支援手術のエキスパートになりたい』という動機で入局する人も多いです。周りとは違う新しいことにトライしたいという人、内科・外科の隔てなくいろいろなことに興味があるというガツガツした人が多いですね。意外に思われるかもしれませんが、女性の医師も珍しくないんですよ。」
こうした若い世代の医師を育てていくことに、大家教授らは並々ならぬ情熱を注いでいます。
「次の時代の泌尿器科医療を前進させていくためにも、若い医師には僕たちを超えていってもらわないと困るんです。だから常に機会均等、互いに切磋琢磨することを大事にしています。そして、困難な局面を1人で乗り越えようとするな、とよく伝えています。凹んだ時もどん底の時も、仲間と一緒にそれを味わい、一緒に這い上がっていけばいいんです。」
「千里の馬は常に有れども伯楽は常には有らず──。この漢詩の通り、才能があってもそれを認め育てる “伯楽” がいなければ、いい医者にはなれません。その点で、ここは医者としての基礎を築く申し分のない環境だと自負しています。慶應の泌尿器科学教室を選んでくれた若者が、ここで素晴らしい先輩に出会って成長してくれること、そして、充実した幸せな医者人生を歩んでくれることを願っています。」

大家 基嗣(おおや もとつぐ)
1987年、慶應義塾大学医学部卒業。1995年、ニューヨーク医科大学泌尿器科留学。1997年、デュッセルドルフ大学泌尿器科留学。1998年、慶應義塾大学医学部泌尿器科助手。2004年、文部科学省研究振興局学術調査官(2006年まで併任)。2007年から慶應義塾大学医学部泌尿器科教授。2013年から、慶應義塾大学病院副病院長も務める。第12回日本泌尿器科学会賞、第6回オルガノン泌尿器科研究奨励賞など受賞歴多数。2023年10月に開催される、第61回日本癌治療学会学術集会の大会長も務める。
※所属・職名等は取材時のものです。