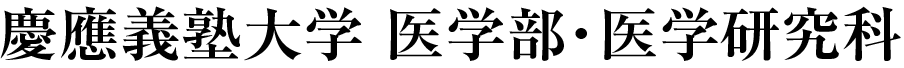医の原点を探れ、世界の広さを見よ
─IMA第44次派遣団、コロナ禍での活動記録─
2022/06/15

45年間受け継がれてきた、医学生の熱い志
── まず、IMAという団体について教えてください。
吉岡 いまから45年前、慶應医学部の学生だった大上正裕先生という方が「世界の大きさを知らぬまま、自分は医師になっていいのか」とお考えになり、学生団体IMA(アイマ)を設立しました。大上先生たちはあえて医療が発展していない南米に足を運び、「医の原点」を実体験するとともに、医学・医療を通じた国際交流に力を注がれました。IMAの志はその後も慶應医学部に受け継がれ、2022年で設立45年目を迎えています。
活動の中心は、6年生の夏休みに約40日間、中南米を中心とした海外諸国での国際医療活動等に参加することです。団員は6年生3名、それをサポートする5年生3名の計6名。団員自ら企業を回って活動資金を集めたり、活動場所・内容を自分たちで考えたりするのもIMAの特徴です。
── みなさんは、なぜIMAに入団しようと思われたのですか。
佐藤 私は学生時代、医学部野球部でひたすら部活動に打ち込んでいたので、学生最後の2年間は新たなことに挑戦しようと思っていました。そんな時、たまたまトレーニングルームに貼ってあったIMAのチラシを目にして、「ブラジルの医療を自分の目で確かめてみたい」という気持ちに駆られたことがきっかけです。
吉岡 私は同じ野球部だった佐藤からIMAの話を聞き、興味を持ちました。先輩方の活動内容を拝読すると「いまの自分にはできないな」と思うことばかり。こんな風になれたら格好いいな、成長できるなと憧れを感じたことが志望の理由でした。
酒井 所属していた医学部競走部の活動が終わるとき、残りの2年間は、学生時代だからできること、特に幼稚舎から慶應義塾でお世話になってきたこともあり「慶應義塾だからこそ成し遂げられること」を経験したいと思いました。IMAはまさにそんな団体でしたし、自分自身を試せる場だと思い、入団を希望しました。
コロナ禍こそ前へ 「国際医学生会議」を開催
── みなさんが入団した2020年は、すでにCOVID-19感染が拡大していた時期ですね。
吉岡 その通りです。5年生の間は、第43次派遣団である6年生の活動をサポートする役割だったので、先輩方がブラジル渡航計画を綿密に練り上げていたこと、ギリギリまで可能性を探りながらも渡航を断念せざるを得なくなったことなどを、すべて間近で見ていました。
酒井 IMA史上初の海外渡航中止という事態でも、先輩方が歩みを止めず動いていた姿は、私たちの目に焼き付いていますし、第44次派遣団として活動する際のなによりの原動力になりました。
── そんな中、新たに創設されたのが「国際医学生会議」ですね。
佐藤 はい。2020年7月、世界8カ国の医学生によるWeb会議「国際医学生会議」を第43次派遣団の先輩方が開催しました。当時はCOVID-19のワクチンもなく、知見も十分に集まっていない時期。各国の政策や医学生のあるべき姿について話し合った会議は、とても有意義な場となりました。
それを受け継ぐかたちで、昨年1月には、私たちが中心となって第2回「国際医学生会議」を開催しました。海外の医学生のバイタリティーや行動力からは、学ぶことが多々あります。たとえば、米・ジョンズホプキンス大学の学生は、COVID-19に関するフェイクニュースの蔓延を問題視し、論文等で調べた正確な情報をInstagramで発信しているとのことで、同年代のそんな姿にはおおいに刺激を受けました。第43次派遣団の先輩方が作った「国際医学生会議」は、今後も続けていく意義があると感じています。
IMA初の国内活動 どこで何をすべきか
── 先の見えない状況下で、第44次派遣団としての活動はどのように決めていきましたか。
吉岡 COVID-19の感染が拡大し始めたばかりの頃は「来年こそ海外に行って先輩方の分も頑張って活動しよう」と考えていました。ですが収束の兆しは見えず、私たちも断念せざるを得ない状況に。複雑な思いも正直ありましたが、逆に「今年しかできないことを」と前向きに気持ちを切り替えるようにしました。
酒井 国内での活動を決める上で指針としたのが、「医の原点の実体験」「医学・医療を通じた国際交流」「変わりゆく社会に即した医療の考察」「COVID-19を通じた感染症への向き合い方への探求」という4つの目標です。さまざまな検討を重ね、離島・僻地医療の現場で医の原点と向き合い、さらに離島医療システムのあり方を考えること、また、在留外国人に対する医療の現場を知ることで、今後の医療支援を考えることを目指し、沖縄の粟国島、長崎の対馬、そして静岡の浜松を活動地に選びました。
── 団長の山岸先生は、この状況をどのような思いで見守っていましたか。
山岸 「海外へ行くべき」「やめた方がいい」などの助言は一切せず、すべて彼らの自由意志に任せていました。団長として私がしたことは、彼らの思いを最大限実現できるように、人を紹介するなどのサポートをしたくらいです。多くの先生方にもお世話になりながら、第44次派遣団の皆は自分たちの力で素晴らしい活動を企画し、実行にこぎつけた。頼もしかったですね。
吉岡 山岸先生が団長でいてくださったことは、私たちにとって本当に心強かったです。活動地が海外から国内になり、その後も変更が重なる中、先生は大変柔軟に対応してくださいました。山岸先生をブラジルにお連れできなかったことはいまでも本当に心残りですが、先生のおかげで実現できた活動も多く、第44次派遣団としてご一緒できたことに心から感謝しています。

浜松で知った、在留ブラジル人の置かれた現実
── 38日間にわたる国内活動は、静岡・浜松からスタートしましたね。
吉岡 少子高齢化の進む日本において、外国人労働者の存在は欠かせません。とくにIMAと深いつながりのあるブラジルから来た人たちは、どういう思いで暮らしているのか、在留外国人はどんな医療支援を求めているのか。それらを探るために、繊維や楽器、輸送用機器などの工場が多く日本最大のブラジル人居住都市でもある静岡・浜松市を2021年7月17日〜24日に訪問しました。
最初に訪れた山口ハート国際クリニックは、院長の山口貴司医師が「医療の手が届かない外国人のために」と設立したクリニック。工場勤務の人が通院しやすいよう土日にも開業し、スペイン語・ポルトガル語の通訳が常駐するなど、外国人患者に寄り添った運営には感嘆させられました。また山口先生は時に冗談を交えたスムーズな会話で、患者さんの心にスッと入り込むコミュニケーションをとる方。午前中だけで40人以上の患者さんが来院されており、信頼度の高さも伺えました。医師が患者さんの生活やそのコミュニティ全体に与えうる影響力の大きさをひしひしと感じました。
ほかにも、カトリック浜松教会、在浜松ブラジル総領事館、静岡文化芸術大学などを訪問し、ブラジル人の日常の一端に触れたり、外国にルーツのある学生の悩みを聞いたりする機会をいただきました。
佐藤 ブラジル人の児童が通う伯人学校イーエーエス浜松校では、ポルトガル語で感染症についての講演を行ったほか、児童のメンタルヘルス調査をしました。子どもたちはみな明るく、学ぶ熱意にあふれているように見えましたが、やはり「言語の壁」「アイデンティティの壁」は大きく、メンタルヘルス問題を抱えている児童は少なくないとのことでした。
また、「将来日本で暮らしたいか」という質問項目に、63%の子どもが「いいえ」と答えたのは衝撃でした。その理由は「日本語ができない」「将来どんな職に就けるかわからない」など。日本人との関わりが少ないため、大学進学やキャリア形成に関する情報もあまり得られないようです。多文化共生という言葉が一人歩きする一方で、実際にはまだまだ課題が多いと感じました。

長崎・対馬の、充実した離島医療システム
── 浜松に続いて、長崎の対馬市へ。対馬での1週間は、どんな活動をされましたか。
酒井 長崎県対馬市は面積708㎢にも及ぶ大型離島で、長年、独自の離島医療政策が実施されてきた地域です。7月25日〜31日、僻地拠点病院での実習や複数の僻地診療所での実習をさせていただきました。
僻地拠点病院である対馬病院にいると、その大きな規模感に離島にいることを思わず忘れそうになりました。リハビリの施設や訪問看護ステーションも隣接されており、心臓血管外科領域と脳神経外科領域を除くすべての医療が島内で完結する仕組みが整っているのです。また、外科の専門医が皮膚科領域の処置もするなど、患者さんを総合的に診る医師の姿にはただただ驚かされました。
吉岡 頭痛の症状を訴えて対馬病院に来られた患者さんのことは忘れられません。私たちが最初に問診した際は肩こりによる頭痛ではないかと思ったのですが、先生のご判断で念のためCT検査をすることに。すると、慢性硬膜下血腫であることが判明し、ヘリで長崎へと救急搬送されていきました。検査ができる環境の重要性はもちろん、自分の診察の甘さを改めて痛感させられました。
佐藤 対馬では、僻地拠点病院だけでなく、僻地診療所が担う役割の重要性も知ることができました。南北に長く高低差もある対馬市では、車移動にも大変な時間がかかります。そこで、複数の僻地診療所を作り、対馬病院等から派遣された医師が近隣住民の慢性疾患などに対応。必要に応じていつでも対馬病院などと連携できる体制が構築されており、そのシステムには感銘を受けました。
酒井 私は対馬で、人材や医療機器をはじめとする医療資源を適正に配分し医療の全体像を変えていくには、やはり「行政の力」が重要だということを感じました。大学での座学や実習では気付けなかった部分であり、僻地医療の現場に行ったからこそ得られた視点だと思います。医師としてのこれからの人生の中で、行政の立場から医療を変えていくという進路も選択肢の一つと考えています。

沖縄・粟国島で考えた、患者との向き合い方
── 対馬から向かったのは、最後の活動地・粟国島ですね。20日間の活動内容を教えてください。
佐藤 8月3日〜23日に訪れた沖縄県島尻郡粟国島は、外周12km、人口700人弱の小さな島です。ここでは、島唯一の医療機関である粟国診療所での外来診療や訪問診療のほか、特別養護老人ホーム、デイサービスなどの見学をさせていただきました。
粟国診療所は医師・看護師・事務員の3人体制で運営されており、島民700人を診る医師はたった一人。夜間でも電話が鳴ればすぐに駆けつけるタフさ、限られた検査しかできない中で正確に診断しなければならない難しさを目の当たりにしました。また、沖縄本島の病院へと救急搬送する際も、一日一便のフェリーを待つか、ドクターヘリや自衛隊へりを呼ぶかといった判断を迫られるなど、離島医療ならではの厳しさを垣間見ることができました。
吉岡 「患者さんと向き合う」という言葉はよく使われますが、私がその意味を心から理解できたのは粟国島での20日間だったように思います。診療所ではかなり長い時間を診察に費やすのですが、先生が患者さんの話をじっくり傾聴し、丁寧に説明をすることで安心して帰っていく姿は印象的でした。また、訪問診療に同行すると、日頃の食生活や室温、衛生状態など、診療所ではわからなかった部分がたくさんあることに驚きました。病院で相対している患者さんの姿はあくまで一面であり、自分にはもっと患者さんを知る努力が必要だと感じました。
いま働いている病院でも、看護師さんや理学療法士さんらほかの医療従事者の方々と協力することで、患者さんともっと深く向き合えたらと思っています。そういった思考を柔軟な学生のうちに持てたことは自分にとっても非常に良かったと感じています。
── 山岸先生は粟国島で活動に合流されたとのこと、同行されていかがでしたか。
山岸 まず、粟国診療所の三宅孝充先生をはじめ、粟国島の方々が非常に好意的に受け入れてくださったことにたいへん感謝しています。実は私自身、若いころに数カ月ほど離島にいたことがあるので、離島医療の実態はある程度わかっているつもりでした。ですが、慶應病院でいわゆる“都会の診療”を長年経験してから訪れると、改めてその違いを感じ、さらに理解が深まったように思います。
学生たちがこれからどんな病院で働く場合でも、そうした離島医療の現実を知っていることは大きな財産になるでしょう。慶應病院をはじめとする病院でも我々はもちろん丁寧に診察していますが、離島では診察に頼らざるを得ない部分がより大きいですし、検査を一つするにも船やヘリで搬送しなければならない。そういった診察の重み、検査の重みを知っていることは大事なことですし、彼らの中にしっかりと刻まれたのではないかと思います。
酒井 38日間の活動の中でも、山岸先生と粟国島で過ごした日々は私の中で特別なものです。山岸先生からは多くの金言を賜りました。一つご紹介すると「医師のプロフェッショナリズムとは何か」というお話。本当のプロフェッショナルというのは、患者さんに寄り添いながらも感情移入はせず、あくまでも中立的な立場で医師として最善の策を出していくことだ、ということを教えていただきました。私には欠けていた部分で、心に突き刺さるものがありました。ほかにもたくさんあるのですが、記事にできないことが多いので控えます(笑)。IMAならではの得難い経験は多々ありますが、尊敬してやまない大好きな先生と長い時間を一緒に過ごせるというのも、その一つだと思います。
山岸 座学などですでに聞いていた話も、実地でさまざまな経験をしたことで、初めて心に入るということはあるかもしれないですね。私は一応教授として若い人に何かを「教え授ける」立場なわけですが、教室の講義だけではここまで近い距離で学生と話すのは難しいものです。医師や研究者として、自分の反省も含めた人生経験を伝えることは、私にとってもいい時間となりました。疲れましたが(笑)、本当に楽しかったです。

「正統と異端」で、道を切り拓け
── IMAの活動を通して得たものを教えてください。また、IMAの後輩に向けてメッセージを。
吉岡 思い通りにいかない時も決して歩みを止めないこと。こんな時だからこそ見える景色があると信じて、一歩一歩進むこと。今後医師として歩む中で、いろいろな困難が立ちはだかると思いますが、IMAで得たこれらの教訓が心の支えになってくれると思っています。
0から1を作っていくというフロンティア精神が、IMAの根本にはあります。私たちは先輩が切り拓いてくださった南米に行くことができなかったけれど、別の場所で自分たちなりの活動を切り拓くことができました。後輩のみなさんも、IMAをより大きくするためのチャンスだと思って新たなことに取り組んでほしいです。応援しています。
酒井 振り返ってみると、IMA初の国内活動を私たちが行うことになったのは、ある種の巡り合わせだったのかなと思います。今後どんなキャリアを歩むにしても、巡り合わせを大切に、そして周りの方々への感謝を忘れずに、前向きに進んでいきたいと思っています。
これから先も難しい状況はしばらく続くかもしれませんが、どのような時でもIMAでしか出来ない経験が絶対にあります。IMAの団員として誇りを持って取り組んでもらえたら嬉しいです。
佐藤 私自身は、医師国家試験の勉強とIMAの活動を両立することで、マルチタスクをこなす能力が鍛えられました。試験勉強を着々と進めている友人を見て焦ることもありましたが、一つひとつ全力で、そして一日一日コツコツと頑張っていけば道は開けるのだと実感しました。
IMAの活動は私たち3人だけの力ではなく、慶應義塾の先生方やさまざまな訪問先の方々に支えていただいて実現したものです。後輩のみなさんも周りの助けに感謝をしながら、果敢に挑戦を続けてほしいですね。ちなみに、私たちはもう医師になってしまいましたが、どうにか時間を作って「いつか3人でブラジルに行こう」と話しています!
── 第44次派遣団の3人、そして今後のIMAへのエールをお聞かせください。
山岸 慶應義塾で大切に受け継がれてきた精神の一つに「正統と異端」を兼ね備えるというものがあります。これがIMA、そして第44次派遣団にふさわしいキャッチフレーズのように思います。というのも、私が学生の頃のIMAは、設立されたばかりのいわば「異端」の組織でした。それが錚々たる団員によって受け継がれて45年が経ち、いまや「正統」の存在となりました。そんな中でしかし、第44次派遣団はブラジル行き断念というIMAにおける「異端」の事態となったわけです。それならば、ここからまた道を切り開き、新しいIMAを作っていけばいい──。彼らはそんなフロンティア精神で、その一歩を見事に実現してくれました。まさに「正統と異端」を備えた、素晴らしい代だったと思います。
先ほど、後輩へのメッセージを彼らは話してくれましたが、私には自分自身へのエールのようにも聞こえました。これから先、大変なことがあってもいまの気持ちを忘れずに踏みとどまってほしいし、彼らならやってくれると確信しています。ますますの活躍を期待しています。