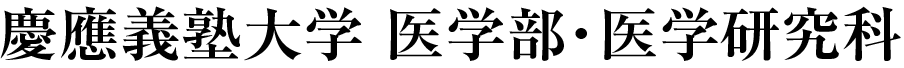世界初、iPS細胞を用いた脊髄再生医療の実現へ【前編】
2022/03/31

脊髄損傷の現実を知ったあの日から
── まず、脊髄損傷の研究・治療に関わるようになったきっかけを教えてください。
中村:僕は医学部時代、バスケットボール部に入っていました。2年生の冬、部の仲間と長野の八方にスキーに行った際、ゲレンデで一つ下の後輩が頸を怪我しました。ただ僕はその時、脊髄損傷がどんな怪我かをわかっていなかった。八方から3時間半かけて救急隊と移動し慶應病院に着いたときは、「これで救われる、手術が終われば治るんだ」と本気で思っていました。
事故からしばらく経って彼の実家を訪ねました。すると彼が、電動車椅子を顎で操作しながら出てきたんです。この時の気持ちはなんと言ったらいいか……。この前まで一緒に部活をやっていた仲間が、肩しか動かない、肘も手も足も動かない。え、どうして?どうして治せないの?という怒りに駆られ、雷が落ちたような感じがしました。
その後、彼は医学部から文学部へと転部し、図書館員として働くことになりました。僕は、脊髄損傷を治せないことへの悔しさを感じるとともに、自分の状況を受け入れ一生懸命生きる彼の姿に、ものすごく影響を受けました。当時は「脊損を治したい」なんて口にこそあまり出さなかったですが、あれから40年経っても気持ちは変わりません。彼の存在が、間違いなくいまの僕の原点ですね。
岡野:私はもともと研究をしたくて医学部に入りました。学生のときは、がん遺伝子の分子学的研究に明け暮れていましたが、すでにマサチューセッツ工科大学(MIT)などで研究が先行していたこともあり進路に迷いがあった。それで、大胆にも国立がんセンターを訪ね、当時研究所長だった杉村隆先生に会いにいったんです。アポなしですから当然、秘書の方に門前払いされるところでしたが、たまたま杉村先生が「なになに?」と出てきてくださって、そのまま30分くらいお話ししました。
杉村先生はがん研究を続けることを勧めるかと思いきや違いました。「いや〜君ね、やっぱり人がやらないことをやるのがいいんじゃないかね。僕はそういう風に生きてきたよ」とおっしゃって、がん研究を牽引してきた先生がいかに独創的な道を切り拓いてきたかを話してくださった。やっぱりすごいなと目から鱗が落ちる思いでした。
「人がやっていない領域」ということで考えたのが、分子生物学の研究手法を使って神経構造を解明することでした。80年代初頭は、神経の研究では形態学と電気生理学以外の手法はほとんど取られていなかったんです。尊敬する脳神経科学者の御子柴克彦先生の勧めもあり、生理学教室に入って神経系の発生の研究をやるようになりました。また実は、大学入学前に、父の知人の脊髄損傷患者の方から「将来はこういう病気を治してほしい」と言葉をかけられていました。結果としてその思いに応える道に進むこととなりました。
神経系は再生しない、その常識を覆した発見
── 岡野先生はその後、15年間にわたって神経発生の基礎研究を続けられますね。
岡野:1983年に大学卒業し、89年にはショウジョウバエの神経発生の研究で米国ジョンス・ホプキンス大学に留学しました。91年には神経幹細胞に発現する分子Musashiを発見。帰国後も研究を続け98年、ヒトの大人の脳にもMusashiが発現する、つまり神経幹細胞があるということを世界で初めて見出し、論文を発表しました。
この神経幹細胞は、ニューロン、アストロサイト、オリゴデンドロサイトなどさまざまな細胞を作るもとになる細胞です。ヒトの大人の脳に神経幹細胞が存在するということは、これまで再生しないと思われていた神経系が再生できるかもしれないということ。論文発表後の世の中の反響は大きく、脊髄損傷や神経難病の患者さんから「なんとか治してほしい」とお手紙をいただくようになりました。
また97年から大阪大学に移ったのですが、当時の医学部長で、免疫学の研究者である岸本忠三先生には大変影響を受けました。岸本先生はIL6というサイトカインを発見され、その受容体に対する抗体は慢性関節リウマチやキャスルマン病の治療薬に役立てられ、最近はコロナの肺炎の治療にも使われています。「基礎研究は臨床に役立ってこそ」「突き抜けた基礎研究は難病を治せる」ということを体現しておられる岸本先生の姿を見て、自分もそうありたいと思い、臨床を目指した再生医療の基礎研究を本格的に始めるようになりました。
始まりは、ワシントンD.C.での再会
── お二人がタッグを組むきっかけは、中村先生の米国留学中の再会だったそうですね。
中村: 脊髄再生の研究をしようと整形外科に入局したものの、当時は「脊髄の再生なんて夢物語」と思われていた時代。国内での研究には限界を感じていました。そこで、周囲の反対を押し切って単身アメリカへ。しかし共同研究を始めた先でも、さまざまな事情で思うような研究ができませんでした。
そんな状況だった99年の春に、当時阪大にいらした岡野先生が査読レビューでNASAに招聘されて、ワシントンD.C.にいらっしゃったんです。それでダレス空港まで岡野先生を迎えに行き、桜が咲くポトマック川のところで近況を話したんですよね。すると岡野先生が「それなら阪大に来て、技術的なことを勉強すれば」と言ってくださって。それから約1カ月間、僕は日本に一時帰国し、阪大で神経幹細胞の培養方法などをみっちり教えてもらいました。おかげでさまざまなノウハウを持ってジョージタウン大学に戻り、研究を続けることができました。あれがなかったら僕は諦めて途中で留学を切り上げていたかもしれません。
岡野:当時は、私も神経幹細胞で脊髄損傷をどう治せるのか考えあぐねていました。中村先生には阪大で細胞の培養方法などの技術的な部分を教えた一方で、私も脊損に関するいろいろなアイディアをいただきました。
中村:あの頃、阪大の研究室から帰る車の中で岡野先生から言われたこと、僕はいまでも忘れていないです。「雅也先生、再生医療はまだカオスなんだよ。誰も出てきてない。ここで突き抜けるしかないんだよ、2人で世界に挑戦しようよ」って。当時夢はあってもまだ何も成し遂げていなかった僕は、その言葉にすごく触発されました。この人と一緒にやったら何かできるんじゃないかと思いました。
岡野:その後、偶然ほぼ同時期に、二人とも慶應に戻ったんですよね。2001年4月には、慶應に新たに総合医科学研究センターができて、中村先生はじめ優秀な研究者たちと、ヒトの神経幹細胞を使った脊髄再生の研究を始めることとなりました。99年にD.C.で中村先生に会ったことは、やはりいろんな意味で我々の研究の出発点でしたね。

閉ざされかけた道を開いた「iPS細胞」の発見
── 神経幹細胞を用いた脊髄再生のメカニズムについて教えてください。
岡野: 「再生」というのは、「発生」をやり直すことです。神経幹細胞を脊髄に移植することによって、ニューロンやアストロサイト、オリゴデンドロサイトなどの発生現象をもう一度繰り返す。すると、途切れていた神経回路が再構築されたり、軸索にグリア細胞が補われて髄鞘が再び形成されたりする。一度損傷してしまった組織が、組織学的に修復し、機能的にも再生していくというわけです。
実際、2000年初めには、「神経幹細胞を移植すると脊髄損傷が治せる」ということを我々はわかっていました。胎児由来の神経幹細胞を脊髄損傷モデルのマウスやサルに移植し、運動機能が劇的に回復することを確認していたのです。
── iPS細胞の発見前から、動物実験では脊髄再生に成功していたんですね。
岡野:はい。次はいよいよヒトへの移植に進めると思ったら、そうはいかなかった。2006年に「胎児由来の神経幹細胞の臨床応用は時期尚早」と判断されたためです。倫理的な規制によって日本では臨床試験までたどり着けないこととなり、フラストレーションを抱えていました。
そんな時、07年に京大の山中伸弥先生がiPS細胞を発見されたんです。論文発表の前からiPS細胞のことは聞いており「これならいける」と確信がありました。その後、山中先生に提供いただいたiPS細胞から神経幹細胞を作製することに成功。さらに12年には、ヒト由来のiPS細胞を脊髄損傷のマウスやサルに移植し、成功しました。

動物からヒトへ、高い障壁を乗り越えて
──実際にヒトへの移植が実現するまでには、この後も多くの困難があったんですね。
岡野:これならヒトに投与できる、という細胞ができるまで、その条件検討になんと約10年もの月日がかかりました。というのも、神経幹細胞は分裂・増殖して神経細胞やグリア細胞を作るわけですが、適切なところで分裂が止まらないと腫瘍になってしまいます。しっかりと生着し組織を修復する、かつ腫瘍化しない細胞を作るために、どれくらいの細胞数を移植しどのような条件で培養すればいいか。その検討に長い時間を要したわけです。
中村: iPS細胞を樹立するというのももちろん世界初の技術ですから、発展途上というか、数年経つとバージョンアップしていくんですよね。より良いiPS細胞ができるのは大変ありがたいことですが、iPS細胞が変われば分化誘導の方法も変わりますし、分化には数カ月かかる。さらに作った細胞を動物に移植し数カ月後に腫瘍化が起きないことを確認する必要があります。年単位で足止めを食うこともしばしばで、この日々は本当に大変でしたね。
岡野:この1年は何だったんだ、No Progressじゃないか……と頭を抱えることが何度もありましたね(苦笑)。さらに臨床研究までには、厳格な出荷判定基準──例えば、ウイルスが混入していないか、がんに関連する遺伝子に変異がないかなど──をクリアする必要もありました。そうやって一つずつチェックを重ね、最終的な評価が終わったのは2020年8月31日のことでした。その後、コロナの感染拡大で患者募集が止まるなど、紆余曲折ありましたが、昨年2021年の12月8日に、ようやく第1症例目の細胞移植を実施することができました。
中村:科学的なこともそうでないこともいろいろありましたが、無駄だったことは一つもないと思います。患者さんに届ける以上、ベストサイエンスを尽くすのが我々のポリシーですから、転んでもただでは起きあがらずしっかりと何かを学んで立ちあがり、ここまでやって来たという感じですね。
岡野:そうですね。本当に長い年月と手間がかかりましたが、一連の過程で蓄積されたさまざまな知識・経験は我々の自信となっています。また、世界初の手術にこぎつけるまでには、慶應義塾大学病院全体、さらに協力医療機関である村山医療センター、京都大学iPS細胞研究所(CiRA)など、慶應内外のチームによって支えられました。非常に有難いことだと思っています。