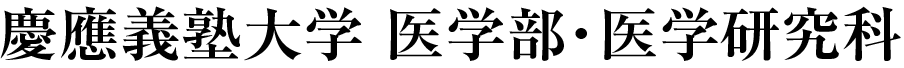これからは病理学でがんを予防する時代
2022/12/29
顕微鏡の中の美しい組織に魅せられて
学生時代、将来の医師人生に思いを馳せた金井教授は、医師として自分の生きた証を残したいと考えていました。
「それには自分にしかできないこと、何かを創造する仕事がしたいと考えました。そこで当初目指していた臨床医ではなく、患者さんに近いところで研究ができればと思うようになったのです。しかし人生はとても長く、これから何十年も研究していくということを考えると先の見えない不安を感じました。」
絶対に朽ち果てない基盤のようなもの、ずっと研究を続けられる根拠のようなものが欲しいと考えた金井教授が自然に行き着いたのが「病理医」でした。
「病理学とは『病の理 (ことわり)を顕す (あらわす)学問』で、顕微鏡でヒトの組織の形態を観察する形態学を基盤としています。目で見て、視覚情報を集約して組織の形態を捉えます。ですから病理学の学生実習では、実際に自分の目で顕微鏡を見て、詳細に組織を観察して色鉛筆でスケッチしたりすることも重要になります。」
金井教授は、顕微鏡写真を集めた組織学の教科書を眺めたり、顕微鏡を見たりすることが好きな学生だったと言います。
「組織には形態があり、そこに機能が宿っていますから、決して無目的には配列せず、秩序だって並んでいます。それは思わず顕微鏡に見入ってしまうほどの美しさです。逆に、組織が美しいのは機能がここにしか宿ることができないためだと考えると、それを扱う形態学を基盤にしていれば、これから研究を何十年続けたとしても、よって立つ基盤を失わずにすむのではないかと考えました。」
20歳で予見した通り、病理学は金井教授の一生のフィールドとなりました。
病理学者の2つの顔
病理学に進む場合、大学院に進み研究を行うことと専門医研修を受けることは、通常同時進行で行われるようになっています。
「医学の中でもこれはほぼ病理学だけの特徴ですが、一般的にあまり理解されていないように思います。そもそも顕微鏡による観察を基盤とする病理学者には、研究を行う研究者としての側面と、患者さんの検体の診断を行う病理専門医・病理診断医(臨床医)としての側面、つまり二面性があるのです。臨床医と研究者では双方の立ち位置があるため、人の2倍仕事しなくてはならなかったり、時には両方から理解されなかったりすることもあります。」
しかし、研究と臨床を同時に行えるところこそ病理学の醍醐味があると金井教授は考えています。
「病院と研究室をつなぐ渡り廊下のような場所に本拠地があるのは難しい立ち位置ではありますが、両方を行っていくことが理想だと考えています。臨床医として患者さんの診療だけを目的に顕微鏡を見るというより、診療という現場で一生懸命診断を行う臨床医の発想で研究を行ったり、逆に患者さんの診断の際に研究者のサイエンティフィックな目で判断しながら診断したりすることができる、それが病理学者の真骨頂ではないかと。要は、研究を基盤として診断したり、診断を基盤として研究したりできるわけです。両方を同時に行うことで、1+1を3以上にすることができると考えていますし、私の研究室には、この考えに共鳴した大学院生が集まっています。病理の道に進むには、最初に病理解剖を1人で執刀できるようになるだけでも大変で、病理専門医試験も、病院ですでに独り立ちして勤務している医師ですら落第することもあるほど厳しい試験です。ですから大学院生たちはそれなりに苦労していると思いますが、それでも研究も臨床も両方やりたいと考える学生たちが集まっているのは喜ばしい限りです。」

病理+分子生物学を求めて国立がんセンター研究所へ
「膠原病の病理を専門とする教授に師事して病態解析のような課題をいただいていましたが、自分みたいな大学院生が今いたら、とても許すことはできないほど勝手なことをやっていましたね。倉庫を改造して勝手に新しい実験室を作ったり、他科の研究者と共同研究を始めてみたり。そして、狭い枠にとどまっていてはいられないと、3年で学位論文の執筆を終え、形態学を基盤にとにかく分子生物学ができるところに行くぞ、ということで、大学院生のうちに国立がんセンター研究所に移ってしまいました。」
ちょうどその時、患者さんの組織検体で分子生物学的な解析が初めてできるようになっていた頃でした。
「日々の病理診断の積み重ねを背景に、研究に同意してくださった患者さんの検体から核酸を抽出し、初めて分子生物学を行えるようにしたラボ、それが国立がんセンター研究所の病理部でした。当時、細胞接着に関する研究に熱心に取り組んでいました。」
がん化では、細胞同士がバラバラになる
「細胞接着は、顕微鏡の中に広がるアートのような美しい組織構築を作る大切な要素です。細胞が隣の細胞と手をつないでいると勝手な行動ができません。細胞が一定の方向にきれいに並ぶことを極性と呼び、極性がきちんとしていれば複数の細胞が共同して機能を果たせます。その極性を維持するには、細胞接着がとても重要なのです。」
つないだ手が離れてしまうと(細胞接着分子の破綻)、細胞同士はバラバラになります。それは細胞同士が構築している社会の美しい秩序が崩れるということで、がん化そのものにも、バラバラになったがん細胞の浸潤にもつながります。細胞と細胞が手をつなぐ役割を果たす細胞接着分子は、細胞が形態を形作るだけでなく、がんの発生・進展の本質に関わるという点でもとても重要だったのです。
「ゲノム(DNAのすべての遺伝情報)が解読されていなかった当時は、細胞接着分子の塩基配列自体がまだ解明されていませんでした。正常な塩基配列がわからないため、まず健康な人のゲノムの塩基配列を調べてデータベースに登録し、次にがん細胞の異常を調べるといった作業を続けていました。」
バラバラの原因は、DNAメチル化にあった
「DNAのメチル化というのは『エピゲノム修飾』と呼ばれる事象のひとつです。ゲノムにささやかな飾りがつくようなもののため、発がんの主役になるようなことはないだろうと考えられていて、あまり重要視されていませんでした。当時はがんが遺伝子変異で生じるという考えが席巻していて、DNAのメチル化を研究している人はとても少なく、研究成果を積み重ねることによって、『本当なの?』というような懐疑的な見方を覆す必要がありました。」
細胞接着の研究チームでの仕事をひと通り経験して30代半ばになっていた金井教授は、独立して研究すべき時期にさしかかっていました。E-カドヘリンがDNAのメチル化で不活化されることを発見したのは、まさにそうした時期でした。
E-カドヘリンという細胞接着因子は、がんをバラバラにしないという性質上、がん抑制遺伝子としての側面を持っています。そのE-カドヘリンがDNAのメチル化で不活化すると金井教授らが発表した当時、がん抑制遺伝子がメチル化で不活化するのはきわめて例外的な事象と捉えられていました。
「稀であったため、あまり意味のないことなのではないかと言われていたほどでした。発がんのメカニズムとして、染色体上の同じ位置にある対になったがん抑制遺伝子の両方が不活化されて初めてがんになるという2ヒットセオリーが提唱されていましたが、不活化するのは、①ゲノムの一部が失われること、②遺伝子変異―という2つの条件がそろった場合だけと考えられていました。ところが、私たちがDNAのメチル化によるE-カドヘリンの不活化を証明したことによって、これが普遍的な事象であり、従来考えられていた遺伝子変異でなくても、DNAメチル化によってがん抑制遺伝子が不活化し、2ヒットセオリーが成立することを示すことができました。」
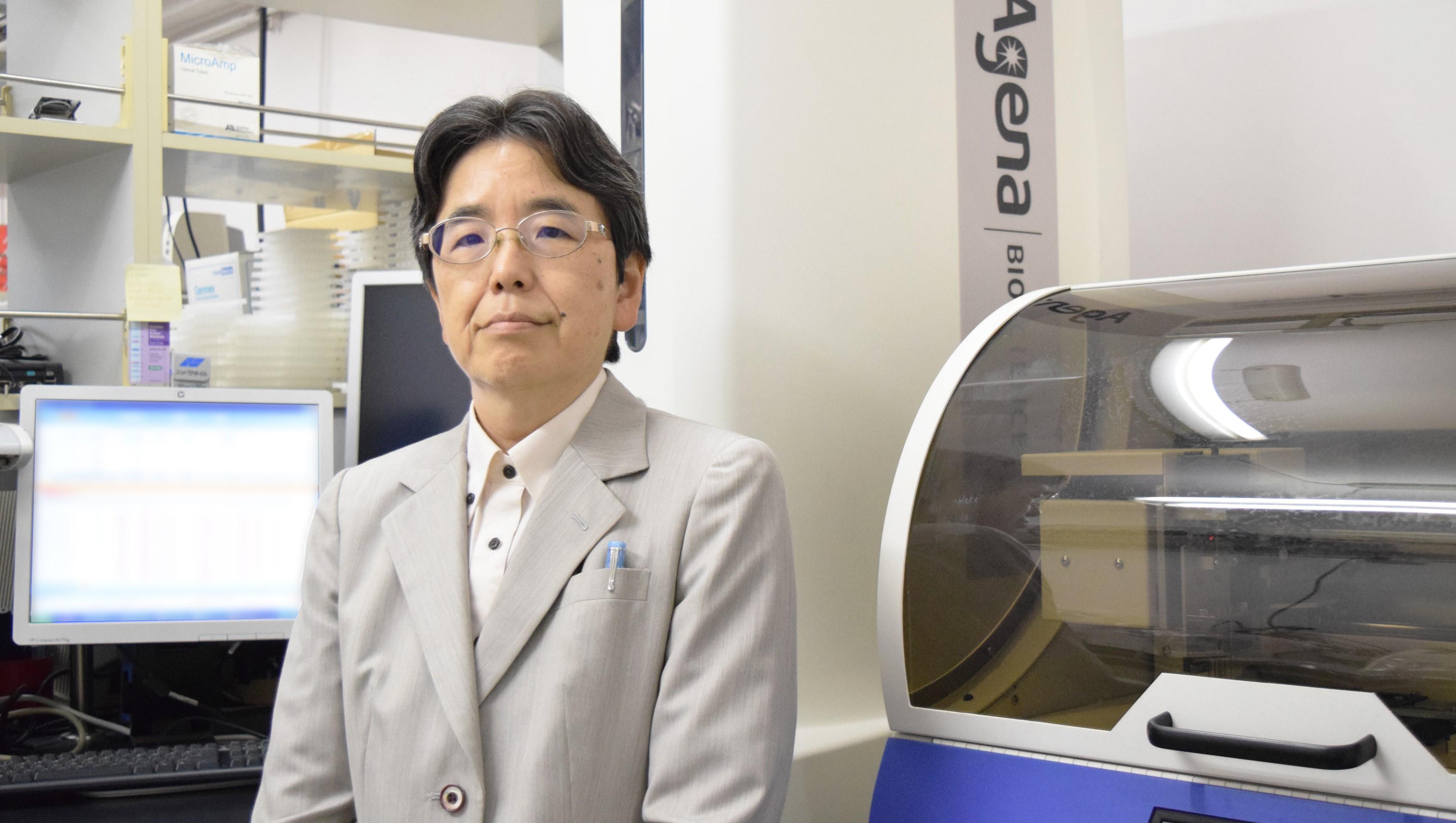
前がん状態ではDNAメチル化異常が起こる
一方で、がんが生じる前の段階も日ごろから顕微鏡で観察していた金井教授は、がんを予防したり治療したりするためには、発がんの早期に何が起きているかを知ることが重要ではないかと考えていました。
「遺伝子変異はさほど早くから起きているわけではないので、それに先行するメカニズムは何かと考えると、やはりDNAメチル化修飾が浮かんできました。DNAメチル化が異常をきたすと、クロマチン構造と呼ばれるものが変化し染色体不安定性を生じるとも言われていて、論理的にも説明がつきました。私たちは顕微鏡を見ていますから、DNAのメチル化で微小環境が大きく変化することや、がん細胞が環境に応じて接着したりバラバラになったりする様子をつぶさに観察していました。他臓器に浸潤し、遠隔転移する時には、血流や周囲の細胞といった『敵』の間をすり抜けなくてはならないので、がん細胞はバラバラになって動き回っています。ところが遠隔臓器に行って勢力を拡大するというときには、個々の兵隊がバラバラではなかなか勢力を拡大できないため、結局『隣の人と協力したほうがいい』ということで、もう1回隣の細胞と手をつなぎ、接着するのです。
メチル化修飾のように、DNAの塩基配列を変えずに細胞が遺伝子の働きを制御する仕組みをエピジェネティクスと呼びますが、世間は注目していないけれどもきっとこのエピジェネティクスこそ発がんにおいて重要なのだと執念深く研究を続けました。私たちは当時から肝がんを研究対象にしていたのですが、肝がんの前がん段階である慢性肝炎や肝硬変で、がんになれば欠失が観察されるような染色体部位に、DNAメチル化異常が先行して起こっているということを、ヒトの検体を使って直接証明できたことは大きかったと思います。」
こうして金井教授は前がん段階でDNAメチル化異常が起こるということを世界で初めて報告し、がん研究を大きく前進させました。今日では、ほとんどのがん抑制遺伝子がDNAメチル化で不活化されることが知られています。
「基本的には、ここが私の独立した研究者としての出発点だと考えています。」
現在、金井教授らは、長年研究してきたメチル化を発がんリスク診断等に応用する研究を進めています。
NASHの発がんリスク検査を開発
現在、金井教授が発がんリスク診断で注目するべきと考えている病気のひとつが、非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)です。
「NASHでは長年肝臓に脂肪が溜まり、炎症が続いているうちに肝硬変となり、やがて肝がんになっていくという病気です。肝硬変が進行して肝がんに進む方は1割強といわれています。代謝性疾患のひとつとみなされ近年増加していますが、最初は症状もなく、診断されても病院に定期的に通ってくださる患者さんは必ずしも多くありません。NASHの診断を確定する時には肝生検を行いますので、その一部を使用し、将来がんになりやすいタイプのDNAメチル化プロファイルを持っているかどうかを測定しようというものです。リスクをお知らせすることでNASHの進行を止めるような治療に取り組んでいただく契機になると思いますし、臨床医の先生方からも要望されていますので、医療実装に向けて開発を続けています。」
これまで金井教授らは、多種類の細胞系列が混在した臨床検体に適した普及させやすい方法を模索し、企業と共同で高速液体クロマトグラフィー(HPLC)による診断方法を開発してきました。
「診断時の肝生検で残った検体を使用するので患者さんに余計な負荷がかからず、HPLC法を適用すれば10分程度で検査結果を出すことが可能です。1回あたりの検査が簡単かつ結果が早くわかるので、患者さんに『NASHの進行を食い止めるための予防を一生懸命行いましょう。そうすれば肝がんにならずに済むかもしれません。』と伝えられるシステムを普及できると期待しています。」
上部尿路がんは尿検査で診断できる時代が来る
「上部尿路がんは、膀胱がんと同じような種類のがんが、腎盂(じんう)や尿管などの膀胱よりも上流に起きる病気です。診断が難しいことで知られ、診断に手間取っている間に病気が進んでしまうことがあります。この上部尿路がんを尿検査だけで診断しましょうという計画を立てていて、多施設共同研究を進めています。国立がんセンターでは泌尿器のがんを専門に診断していたため、泌尿器科の医師とはいつもカンファレンスや電話でコミュニケーションを取り、『いつもと違う書き振りの病理診断の報告書が出てきたけど、この患者さんの標本を顕微鏡で見せてもらえますか?』と泌尿器科医が訪ねてきてくれるといった付き合いをずっとしてきました。その頃の若手の泌尿器科医が、いまは全国で指導的な立場で働いておられ、その先生方と泌尿器科コンソーシアムを作って研究を行っているところです。現在までに達成している感度・特異度は非常に良好で、役に立つものになるだろうと考えています。」
病理画像情報と分子情報の使い手として
「分子情報がビッグデータであることは周知の事実ですが、実は『形態』も一種のビッグデータです。これまで形態に関わるデータを統括する手段は顕微鏡ぐらいしかなかったため、特別な訓練を受けた病理医が、形態に反映されたビッグデータを顕微鏡を通して統括し、がんを診断してきたと言えます。顕微鏡で見るということは、形態異常の背景にある膨大な数の遺伝子の異常を総合して見ていることになります。一方、現在盛んに行われるようになったオミックス解析は、たとえば膨大な数の遺伝子のDNAメチル化状態を総合してプロファイリングを行うもので、顕微鏡で見ることの本質と相通じる部分があります。そのような形態と分子情報を人工知能 (AI)を用いた深層学習で統合し、新しいゲノム医療を創出できる可能性もあると思います。新しいゲノム医療を創出していく研究は、分子情報と形態学の両方ともに真剣に向き合ってきた、病理医であり研究者である私たちの、真骨頂と考えています。」
金井 弥栄(かない やえ)
1989年慶應義塾大学医学部を卒業。1993年同大学大学院医学研究科博士課程 (病理系病理学専攻)を修了し、国立がんセンター研究所病理部研究員となる。2002年国立がんセンター研究所病理部長を経て、2010年 国立がん研究センター研究所分子病理分野長ならびに国立がん研究センター研究所副所長(~2014年)を兼任。2015年慶應義塾大学医学部病理学教室教授に就任し、現在に至る。2021年より慶應義塾大学医学部副医学部長。
※所属・職名等は取材時のものです。