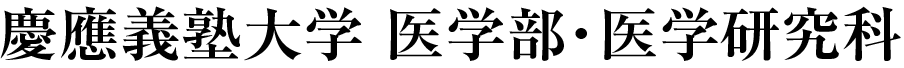生きた臓器のミニチュア「オルガノイド」で加速する難病研究
2019/12/20

人類の歴史上、流行する病気の種類はダイナミックに移り変わってきました。現代は、今や国民病となったがんだけでなく、希少疾患と言われていた潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患に苦しむ人が年々増加し、一日も早い治療法の確立が望まれています。
慶應義塾大学医学部坂口光洋記念講座(オルガノイド医学)佐藤俊朗教授らの研究チームは、根治できる治療法がまだ見つからず、病気のメカニズムもよく知られていない潰瘍性大腸炎の謎に迫る研究結果を科学雑誌Natureに発表しました。佐藤教授らが世界で初めて開発したオルガノイドの培養技術により、治療法のなかったさまざまな病気の成り立ちが解き明かされつつあります。
培養皿の上の小さな臓器(オルガノイド)で発見した潰瘍性大腸炎の特徴とは?
オルガノイドとは「器官(organ)」と「~に類似したもの(-oid)」の造語で、生体内の細胞で見られる立体的な3次元構造を形作るよう培養された細胞の塊のことを指します。いうなれば培養皿の上に育った、生きた小さな臓器のようなものです。このオルガノイドを使うことで、病気になってから細胞を研究するのとは違い、正常な細胞が変化していくメカニズムを研究することが可能となりました。
潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜が原因不明の炎症を起こして潰瘍やただれ(びらん)が生じる疾患です。多くの場合、血の混ざった下痢や血便、腹痛などがみられ、症状は悪化したり落ち着いたりを繰り返していきます。このため長期療養が必要とされ、厚生労働省の指定難病に認定されています。以前は珍しい病気でしたが、近年、日本の患者数は約17万人(平成25年度末の医療受給者証および登録者証交付件数の合計)に増加しています。
佐藤教授の研究チームは、潰瘍性大腸炎をオルガノイドを用いて研究した結果、炎症を起こしている大腸上皮細胞では炎症を促すインターロイキン17(IL-17)というサイトカイン(タンパク質の一種)に対し鈍感となるような特異的な遺伝子変異が蓄積していることを、世界で初めて明らかにしました。
細胞はなぜ、どのように病気になっていくのか
「物理学者ファインマンは『私は自分に作れないものは、理解できない』と言いました。実は病気にも同じことが言えるのではないかと考えています。例えばヒトの研究では、通常、患者さんの病変から細胞を採取して観察・研究しますが、それは病気が起きた結果を見ているにすぎません。例えば潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患の場合、さまざまな免疫が炎症を起こし、腸の細胞が破壊されています。しかしこの荒れ果てた腸を見ても、元は正常だった腸がどのようにして荒野のような状態になったのかということは分からないわけです。」
慶應義塾大学医学部を卒業し、同大学院で炎症性腸疾患を研究していた佐藤教授は、腸の再生の研究を始め、2005年に米国のStowers研究所、2006年にはオランダのHubrecht研究所に留学し、帰国後は消化器がんの研究も行ってきました。
「Hubrecht研究所ではハンス・クレバース博士が腸の幹細胞をまさに発見したという論文をまとめているタイミングで、私は腸の幹細胞をいかに培養するかを研究し、培養に必要な3つの因子の特定に成功しました。こうして開発された幹細胞培養技術はやがて、ヒトの他の多くの臓器や種を超えても応用できるものであることが分かったのです。」
これまで、遺伝子の研究は主にマウスを使った動物研究に依存してきましたが、動物研究を縮小し、オルガノイド研究に軸足を置く動きが世界的に広まり、今ではオルガノイド関連の研究会が世界各地で数多く行われるようになりました。この動きは動物愛護の観点からも、社会に広く歓迎されています。
がん細胞を作ってみる
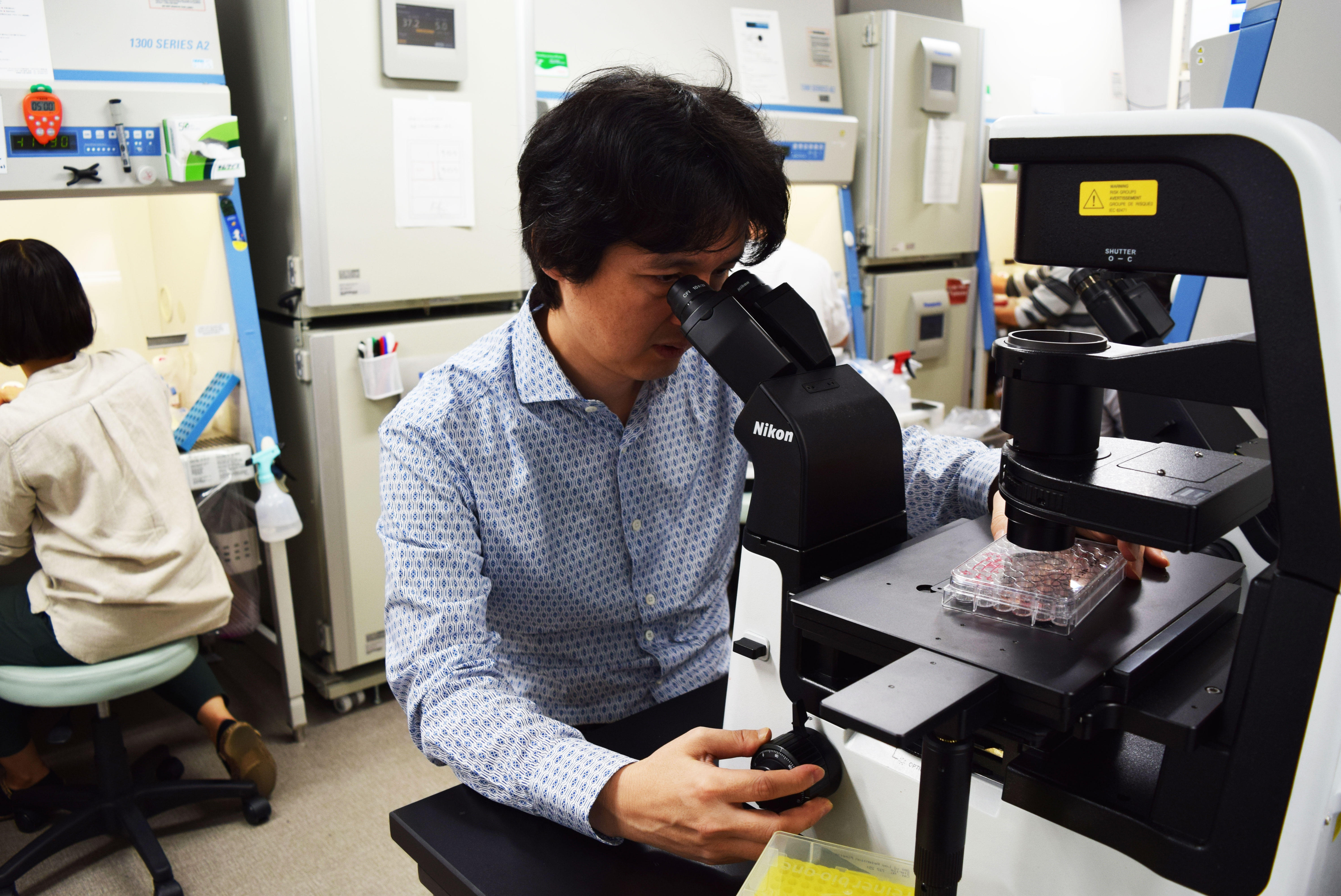
現在、佐藤教授は大腸上皮細胞のオルガノイドを培養し、正常細胞が潰瘍性大腸炎や大腸がんになっていくメカニズムを研究しています。
「まさにオルガノイドを使って、がんや潰瘍性大腸炎を『作って』みています。通常、例えばがんや炎症がある場合には、すべて目による観察でさまざまな病名に分類し、遺伝子を解析して研究してきたわけですが、オルガノイドを用いることで、正常な細胞が生き物としてどのように変化するのかを観察することができるようになりました。私たちは正常な大腸上皮細胞がどのように病気になっていくのかというプロセスを検証しているわけです。 これまでに、正常な大腸上皮細胞は、非常に良質かつ豊富な種類の『細胞の餌(増殖因子など)』が与えられないと育たないばかりか、生育エリアも基底膜の上という決まった場所のみに限られることが分かっています。 一方、大腸がんの上皮細胞は、種類が少なくごくわずかな『餌』でも、本来腸の上皮細胞が育つ条件にはない腸の深部や筋肉、さらには他の臓器でも育つ雑草のような特徴を持っています。生きていくのに必要な『餌』が徐々に減っていき、か弱い正常な細胞が、何もなくても生きられるがん細胞に変化していった可能性が考えられました。」
さらに、細胞をがん化させる新たな要因の存在も浮かび上がってきました。
「たとえばがん細胞を正常細胞から作ってみると、従来言われていたことだけではがんが成立しないことが明確になりました。がん細胞に特異的なことで知られる遺伝子変異を正常な大腸上皮細胞に4つ、5つと入れていくと、実際、餌が少なくても育つ雑草のような細胞にはなります。しかしそれだけでは、浸潤や転移という特徴を持つ正真正銘のがん細胞にはなりませんでした。作ってみて初めて、似ているけれども足りない部分が分かってきたわけです。今はもう一回立ち戻ってさらに必要な因子を検討し、最終的に本物のがん細胞にどんどん近づけていくというステップを続けています。」
細胞の生みの親-幹細胞のゲノム年齢
オルガノイドを使った研究により、幹細胞の加齢現象も見えるようになりました。 私たちの体では細胞が絶えず生まれては死に、新しい細胞に置き換えられています。この新しい細胞を生み出しているのが、幹細胞です。複数の幹細胞からクローンが生まれているため、ある一つの幹細胞から生まれたクローンだけを研究することは以前はできませんでした。しかし佐藤教授らが開発した腸管上皮幹細胞のオルガノイド培養技術では、1個の幹細胞から多数のクローンを増殖させることができます。こうして佐藤教授は幹細胞1個あたりでどの程度の遺伝子変異が生じていくのかについて、ゲノムシーケンスを用いて調べた研究も報告しています。
「幹細胞は分裂を繰り返し、そのたびに遺伝子が複製されます。しかし腸の幹細胞は何億個もあり、それが毎日分裂するたびに遺伝子の複製ミス、すなわち遺伝子変異が少しずつ積み重なっていきます。私たちの研究から、ヒトの体内では、大体毎週1個、1年に約40個の遺伝子変異が生じることが明らかになりました。これは誰にでも起こり、避けることはできません。 変異の数を数えれば、いわゆる細胞の『ゲノム年齢』が分かります。私たちの体のほとんどの細胞は経年的に変異が蓄積するため、年齢に応じて変異の数が増えていきます。例えば、大腸幹細胞は40歳であればおよそ3,000個の変異が入っていることがわかっています。従って、大腸幹細胞の変異数が3,000個であった場合、実年齢に関わらず、腸のゲノム年齢は40歳と推定することができるのです。」
次に佐藤教授は、ゲノム年齢に影響を与える因子を探す手始めとして、潰瘍性大腸炎の炎症がゲノム年齢に与える影響を検討しました。それが今回、潰瘍性大腸炎の知られざる遺伝子変異の発見につながることになりました。
「病気というのは明確な境界があるわけではなく、徐々に徐々に進行していきます。これはそのごく初期の目に見えない部分の変化に焦点を当てた研究です。 潰瘍性大腸炎では、炎症が左右の片側だけに広がっている症例があります。今回、私たちは、こういった同一の患者さんの正常上皮細胞と炎症部分の上皮細胞について、オルガノイドを使い遺伝子変異を比較しました。 その結果、炎症部分では確かに正常上皮細胞に比べて遺伝子変異は多かったのですが、数としては予想していたほどの差ではありませんでした。しかし、その変異の種類を調べてみると、潰瘍性大腸炎の炎症細胞には、今まで知られていなかった特徴的な遺伝子変異が起きていることが明らかになりました。」
炎症環境への適応現象?

細胞はサイトカインというタンパク質を分泌して、他の細胞にさまざまな信号(シグナル)を送り、コミュニケーションしています。潰瘍性大腸炎では炎症が広がっていきますが、このときには炎症を促すように働く炎症性サイトカインがたくさん分泌されています。
佐藤教授によれば、このような炎症性サイトカインが多い状態は、正常な大腸上皮細胞にとっては元来非常に住みにくい環境であるそうです。
「正常な大腸の上皮細胞は、通常は炎症性サイトカインにさらされていなく、逆にさらされれば死んでしまいます。しかし潰瘍性大腸炎の炎症部分にある上皮細胞では、『炎症を促進しろ!』というメッセージを出す炎症性サイトカインの一種であるインターロイキン17(IL-17)だけに反応しないような遺伝子変異が積み重なっていることが分かりました。私たちの幹細胞には年齢とともに遺伝子変異が積み重なっていきますが、通常、その変異はあくまでランダムなもので、バラエティーに富んでいます。しかし潰瘍性大腸炎の腸を見てみると、特定の遺伝子が変異した細胞だらけだったのです。このことから、潰瘍性大腸炎になると、炎症環境に弱い正常細胞が減少していき、炎症に耐えられるよう変異した細胞が増えていく——上皮細胞が徐々にIL-17をブロックする遺伝子変異を持った細胞に塗り替えられていくという可能性が考えられました。」
しかし、この変異の蓄積は直接がん化に結びつくものではないそうです。
「私たちのような研究医にとって、医学研究の醍醐味は、病気がなぜ、どのように起こっているのかを解明することにあります。大腸の上皮細胞自体は炎症性シグナルに強くなっていっても、そうした炎症性シグナルに反応しないままシグナルが飛び交う環境が長年続くと、腸全体の炎症は悪化してしまうのかもしれません。今後さらなる研究を続け、いずれ全容が明らかにできればと思います。」
潰瘍性大腸炎は大腸がんに進行しやすいことが知られていますが、今回発見された遺伝子変異の蓄積は、腸全体の炎症にとって良い影響をもたらすのでしょうか。それとも、悪影響となるのでしょうか。また、ここからどのようにしてがんへの変化が生じるのでしょう。佐藤教授のオルガノイド技術が可能とした新しい発見は、次々とさらなる新しい問いへとつながり、疾患の成り立ちに迫る研究を世界中で生み出しています。これまで全く原因の分からなかった難病研究に、いま新しいドアが開かれ始めています。

佐藤 俊朗(さとう としろう)
1997年慶應義塾大学医学部卒業。2004年慶應義塾大学大学院医学研究科 博士。2005年よりStowers研究所(米国)博士研究員、2006年よりHubrecht研究所(オランダ)博士研究員。2013年慶應義塾大学医学部内科学(消化器)特任准教授。2016年慶應義塾大学医学部 内科学(消化器)准教授。2018年より慶應義塾大学医学部坂口光洋記念講座(オルガノイド医学)教授。
※所属・職名等は取材時のものです。