Young Researchers' Trip report
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- Keystone Symposia -Mechanism and Biology of Silencing-
(2011年3月20日~2011年3月25日) - Keystone Symposia (Stem cells, cancer and metastasis)
(2011年3月6日~2011年3月11日) - Keystone Symposia (Stem cells, cancer and metastasis)
(2011年3月6日~2011年3月11日) - 第7回日本消化管学会総会学術集会
(2011年2月18日~2011年2月19日) - 短期留学生(研修)受け入れ University of Birmingham, UK → 生理学
(2011年1月22日~2011年2月12日) - 第6回オートファジー研究会
(2011年1月12日~2011年1月14日) - 33rd Annual San Antonio Breast Cancer Symposium
(2010年12月6日~2010年12月10日) - 52nd ASH(American Society of Hematology) Annual Meeting
(2010年12月3日~2010年12月8日)
- Keystone Symposia -Mechanism and Biology of Silencing-
ホーム > Young Researchers' Trip report > Keystone Symposia -Mechanism and Biology of Silencing-
Keystone Symposia -Mechanism and Biology of Silencing-
氏名
平野 孝昌
GCOE RA
分子生物学
詳細
GCOE Young Researcher Support Plan(2010年度)
参加日:2011年3月20日~2011年3月25日
活動レポート
今回私は、アメリカのカリフォルニア州モントレーという、西海岸にある港町で開かれた学会に参加してきました。アメリカ西海岸といえば、眩し過ぎる太陽とどこまでもブルーな空を想像し、その陽気な天気を拝めることを期待して胸を膨らませていました。しかし、実際に行ってみたら行程期間中ほとんど雨で、特に早朝はバケツをひっくり返したような勢いで降り、大雨の音で目を覚ましたことも何度かありました。また、モントレーにはサンフランシスコ国際空港からアメリカ国内便の飛行機を乗り継いで行くのですが、雨の影響か飛行機が飛ばず、サンフランシスコ国際空港内で8時間も待たされ、その挙句、乗った飛行機がたった30人程度しか乗れないとても小さな飛行機で、雲の中に突入する度に機体が大きく揺れ、ホテルに到着した時にはもうグッタリしてしまいました。しかし、さすがは港町なだけあり、蟹やサーモンなどの海産物をふんだんに用いた食事はとても美味しく、ご飯を食べてすぐに元気を取り戻しました。ただ、行程期間の後半は、その味に少し飽きてしまいましたが...。やはり日本食が一番自分に合っているなと再確認です。

さて、今回私は、小分子RNAによる生物学及びその生合成機構についての学会に、ポスター発表と、最新の知見を得る為に参加してきました。小分子RNAが関与する遺伝子発現制御機構を総称して、RNA silencingと呼びます。RNA silencing機構は、10数年前に発見された比較的新しい分野で、生物にとって重要な機構であるのですが、まだまだ分かっていない事がたくさん存在します。小分子RNAといっても色々なものがあり、代表的なものを挙げると、mRNAに作用し遺伝子発現抑制に関わるmicroRNAやsiRNA、生殖幹細胞の維持やトランスポゾンの抑制に寄与するpiRNAなどです。しかも、small RNAの機構は様々な生物種に広く保存されており、ヒトやマウスの研究発表はもちろんのこと、ショウジョウバエやカイコ、線虫やら植物、さらには酵母やカビと、モデル生物は多種多様です。それだけに、生物における小分子RNAの重要性が伺えます。
学会で興味を持った内容をいくつか挙げますと、まずはmicroRNAの遺伝子発現抑制機構についてです。microRNAは、相補的な配列をもつmRNAと結合することで、そのタンパク質の発現を抑制します。現在は、mRNAのポリ(A)短縮化とmRNA分解因子の誘導によってmRNAが不安定化するというのが主流になっていますが、リボソームの解離による機構を唱える発表もあり、未だにホットな話題であると感じました。
piRNAに関しては、その生合成に関わる発表が多くありました。piRNAは、生殖組織特異的なsmall RNAです。そのうち、新たな遺伝子を発見したという報告がありました。ショウジョウバエのpiRNA経路に関わると考えられる遺伝子の名前は、Aubergine (なすび)、Squash (きゅうり)、Gurken (カボチャ) など、野菜の名前がよく用いられています。今回piRNA経路に関わる新な遺伝子には、Avocado(アボカド)という名前が付けられ、また野菜(果実!?)の仲間が増えました。また、ミトコンドリアに局在するZucchini (ズッキーニ) というタンパク質がpiRNA生合成に関わることが、様々な生物種で報告されました。ミトコンドリアは全ての細胞に存在するのですが、それが生殖組織特異的なpiRNAの生合成に関わるというのには驚きを感じます。もしかすると、ミトコンドリアは組織によって異なる機能を有するのかもしれません。しかし、piRNA生合成や機能に関して分からないことがまだまだ沢山あるので、今後も更なる因子(野菜!?)が挙ってくることを予感させます。
その他に、私が実際に研究を行っている、幹細胞とmicroRNAに関するテーマも、いくつか発表されていました。iPS細胞樹立効率を促進する新たなmicroRNAの発見。ES細胞やiPS細胞、がん細胞で高発現しているmicroRNAは、がん抑制遺伝子の代表格であるp53やその経路に関わる因子を抑制することなど、とても内容の濃いものでした。さらには、細胞周期や発生段階に関わるmicroRNAなど、非常に興味深い発表が沢山ありました。
私は、幹細胞とmicroRNAに関してのポスター発表を行いました。ポスター発表では、研究者同士が面と向かって話す事ができ、特に同様の実験を行っている方とは、実験の進め方や実験データの解釈等の討論ができ、有意義な時間を過ごす事が出来ます。今回の発表では、自分では気付いていなかった視点の意見を頂き、とても参考になりました。また、この学会が東日本大震災の直後だったこともあり、研究内容の話の次に、私が日本人であることを確認すると、「お前のFamilyは大丈夫だったか?」「友達は無事か?」「津波の被害をTVでみて、私もとても悲しい」など、たくさんの温かい言葉をかけて頂きました。私も、震災直後だったこともあり、日本を離れて学会に参加すべきか迷う気持ちがあったのですが、ひとりの日本人として、会場で各国の方々からこのような言葉に触れることができ、とても励みになりました。
本学会に参加して、最新の研究成果に触れることができ、驚きや刺激を感じると共に、研究へのさらなるモチベーションと、日本人であることを実感するとても良い機会になりました。今後はさらに研究を進めるべく邁進したいと思います。また、震災に関して、日本人だけでなく、様々な国の人たちが応援してくれていることが実感出来ました。この学会を通して、私が協力出来ることに目を向け、復興の一助になるような行動を心掛けたいと、思いを新たにしました。最後に、このような貴重な機会を与えてくださった幹細胞GCOE関係者の皆様に心から感謝致します。
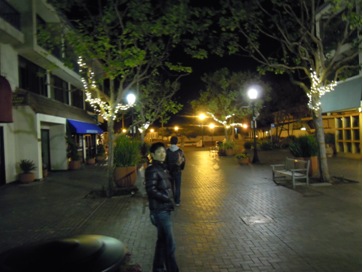
Copyright © Keio University. All rights reserved.
