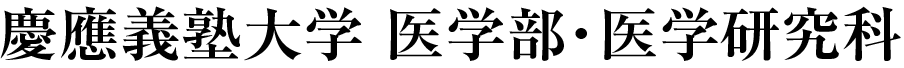学位
医学博士
主な研究領域
ヒト生殖細胞、初期胚発生、エピジェネティックス
略歴
| 2004年 | 北里大学 理学部生物科学科卒業 |
|---|---|
| 2006年 | 慶應義塾大学大学院医学研究科医科学専攻 修士課程修了 (松尾光一研究室) |
| 2010年 | 慶應義塾大学大学院医学研究科生理系専攻 博士課程修了 (松尾光一研究室) |
| 2008-2010年 | 日本学術振興会 特別研究員DC2 |
| 2010-2011年 | グローバルCOE Step-Up Post-doc (慶應義塾大学医学部 松尾光一教授研究室) |
| 2011-2012年 | 日本学術振興会 特別研究員PD |
| 2011-2018年 | ケンブリッジ大学ガードン研究所 リサーチフェロー (Azim Surani研究室) |
| 2018-2022年 | ケンブリッジ大学ガードン研究所 上級研究員 (Azim Surani研究室) |
| 2022-2023年 | 慶應義塾大学医学部医化学教室 助教 (末松誠研究室) |
| 2023-2025年 | 公益財団法人実中研 バイオイメージングセンター 代謝システム研究室 室長 |
| 2025年-現在 | 慶應塾大学医学部分子生物学教室 教授 |
受賞・特許
| 2017年 | 英国 Medical Research Council (MRC), Research grant award (Co-applicant) |
|---|---|
| 2024年 | 日本学術振興会賞 |
研究内容
ヒトの生命は、卵と精子といった生殖細胞の受精から始まり、巧みに制御された発生過程を経て、誕生から成熟、そして老化へと一方向に進みます。しかし、個体内で共に加齢した生殖細胞は、受精を経て一旦リセットされ、いわば若返ります。このように特殊な生殖細胞は、「生殖ライン(Germline)」として世代交代の連鎖による生命連続性を担っており、生命の起源から、長い進化の歴史と現代生物の多様性を生み出してきました。ヒトの生殖ラインの研究は、生命やヒトの根源的な謎に迫るとともに、生殖や妊娠などリプロダクションの理解にもつながり、生命科学や基礎医学の発展において重要な課題です。我々は、ヒトの生殖細胞ラインである、初期発生や生殖細胞発生に着目し、細胞・分子制御機構を解明するとともに新たな研究基盤を構築し、その知見をもとに医療応用への道筋を見つけることを目指しています。
これまでの研究では、ヒト生殖細胞の大元となる雌雄共通の前駆細胞、始原生殖細胞(Primordial Germ Cell, PGC)の発生について解析を進めてきました。これは、受精後およそ2週間のごく小さなエピブラスト胚で起こるため、実際に観察することは非常に困難です。そこで、より初期の胚盤胞から樹立されるヒト胚性幹細胞(ES細胞)や、類似した性質を持つiPS細胞に着目し、高効率のヒト始原生殖細胞運命決定モデルの樹立に世界に先駆けて成功し、研究分野のブレイクスルーとなりました(Irie N et al., Cell, 2015(Best of Cell 2015))。この研究モデルを活用し、マウス生殖細胞発生には不要な転写因子SOX17が、ヒト始原生殖細胞の運命決定において不可欠な役割を持つことを示しました。運命決定後の始原生殖細胞は、胚体内を移動し、後に卵巣や精巣となる生殖巣に到達し、エピジェネティック再構成を経て次世代への情報を構築します。我々は、これらの発生に重要な関連因子を同定し、高効率の移動性および生殖巣始原生殖細胞様細胞誘導の新規培養系確立に成功しました(Irie N et al., Nat Cell Biol, 2023)。さらに、転写因子DMRT1が始原生殖細胞発生に特徴的なDNA脱メチル化プロセスに関わり、DNAヒドロキシメチル化修飾に直接結合して、遺伝子発現やトランスポゾンエレメントの制御に関与する新規エピジェネティック制御モデルを明らかにしました。
これらの研究基盤を軸に発展させ、ヒト生殖細胞ラインのさらなる理解と研究プラットフォームの開発を目指します。特に、始原生殖細胞の維持や成熟、そしてその異常による腫瘍化に着目しています。また、生殖ラインの一部として重要な、着床前後胚発生における細胞と分子特性の変化や、着床前胚発生モデルの樹立と制御機構の解明も目的としています。これらの知見を通じて、生殖補助医療やがん治療、老化医療、さらに再生医療や細胞・ゲノム医療の発展に貢献すること目指しています。
1)ヒト生殖細胞の発生と成熟、その異常による腫瘍化のしくみを探る
Understanding the mechanisms of human germ cell development, maturation, and tumorigenesis
発生した始原生殖細胞は、生殖巣に到達すると胎生期に雌雄それぞれに特異的な発生経路をたどり、生後思春期にかけて成熟し、卵や精子として生殖細胞の機能を発揮します。しかし、発生初期の始原生殖細胞が何らかの原因で正常に発生できなくなると、生殖細胞腫瘍へと形質転換することが知られています。胎生期には胚性腫瘍であるテラトーマや卵黄嚢腫瘍(yolk sac tumor)、絨毛癌(choriocarcinoma)などを形成し、発育不全を引き起こす場合があります。また、この異常は成人において精巣腫瘍、また、まれに卵巣腫瘍として発症することもあります。さらに、始原生殖細胞の移動に異常が生じると、生殖巣以外にも到達します。松果体など中枢神経系で腫瘍を形成すると、小児に多く見られる脳腫瘍ジャーミノーマ(germinoma)として現れることもあります。こうした症例は、日本を含むアジア地域で比較的多いことも知られています。
しかしながら、始原生殖細胞が腫瘍化する仕組みやその増殖機構はいまだ十分に解明されていません。私たちは、開発した始原生殖細胞誘導系を用い、遺伝子解析、エピジェネティクス、代謝といった多角的な視点から研究を進めています。これにより、生殖細胞の正常な発生と腫瘍化の違いを明らかにし、生殖細胞生物学の理解を深めるとともに、診断法や治療法の改善・開発に貢献することを目指しています。
2)着床時ヒト胚のエピジェネティックおよび代謝ダイナミクスの制御とその生物学的意義を紐解く
Regulation and Significance of Epigenetic and Metabolic Dynamics in Peri-implantation Human Embryos
受精後約5日目の胚盤胞が母体の子宮内膜に着床すると、母体と胚の間で栄養や酸素などの交換が可能となり、胎児へと発生が進みます。ところが、ヒトの着床成功率は、自然妊娠においても生殖補助医療においても40~50%程度と極めて低く、妊娠成立のボトルネックとなっています。しかしながら、その着床率の低さや、着床に至る細胞および分子メカニズムは十分に解明されておらず、その改善に向けた研究の障壁となっています。
我々は、着床前後のヒト胚細胞において、遺伝子発現パターン、エピジェネティクスや代謝状態がダイナミックに変化する現象に着目し、それが胚の生存と深く関わる可能性を見出しました。そこで、着床前後ヒト胚発生の細胞培養モデルを用いたマルチオミクス解析や生化学的アプローチ、さらに三次元ヒト初期胚モデルの応用と検討を行っています。これにより、ヒト胚の着床期におけるDNAメチル化やヒストン修飾といったエピジェネティクス変化や細胞内代謝物の動態や制御機構を解析し、胚の細胞運命決定や発生プログラムにどのように関与しているかを明らかにします。この知見は、ヒト胚発生の基礎理解のみならず、不妊症や流産の原因解明、さらには着床成功率向上など生殖補助医療の改善・開発にもつながることが期待されます。
3)ヒト着床前初期胚発生モデルの構築と分子制御メカニズムの探究
Modeling Human Pre-implantation Embryos to Address Molecular Regulation
ヒトの着床前初期胚発生は、受精卵から始まり、割球分裂を経て着床可能な胚盤胞を形成していく極めて重要でダイナミックなプロセスです。その過程では、エピジェネティック再編成を含む、全能性のリプログラミング、胚性遺伝子発現の開始、細胞運命決定や胚体外組織の分化など、多様なプロセスが精緻に制御されています。
しかし、ヒト着床前胚に関する研究試料は限られており、その分子制御機構の解明は困難を伴います。本研究では、ヒト幹細胞培養技術を応用することで、高汎用性なヒト着床前初期胚発生培養モデルの樹立を目指します。この研究により、受精から割球発生および胚盤胞に至る初期胚発生の分子制御ネットワークを明らかにし、生殖補助技術や胚培養技術の改善と開発に資する研究基盤の構築を目指します。
代表論文
- Irie, N.#*, Lee, S.-M.#, Lorenzi, V., Xu, H., Chen, J., Inoue, M., Kobayashi, T., Sancho-Serra, C., Drousioti, E., Dietmann, S., Vento-Tormo, R., Song, C-X., Surani, M.A.*, (#Equal contribution, *Co-corresponding authors), (2023).
DMRT1 regulates human germline commitment.
Nat Cell Biol 25:1439–1452. - Tang, W.W.C.#, Castillo-Venzor, A.#, Gruhn, W.H.#, Kobayashi, T., Penfold, C., Morgan, M. D., Sun, D., Irie, N., and Surani, M.A.*, (2022).
Sequential enhancer state remodelling defines human germline competence and specification.
Nat Cell Biol 24, 448–460. - Kobayashi, T. #, Zhang, H. #, Tang, W.W.C., Irie, N., Withey, S., Klisch, D., Sybirna, A., Dietmann, S., Contreras, D.A., Webb, R., Allegrucci, C., Alberio, R., Surani, M.A.* , (#Equal contribution), (2017).
Principles of early human development and germ cell program from conserved model systems.
Nature 546, 416–420. - Tang, W.W.C.#, Dietmann, S.#, Irie, N., Leitch, H.G., Floros, V.I., Bradshaw, C.R., Hackett, J.A., Chinnery, P.F., and Surani, M.A.* , (#Equal contribution), (2015).
A Unique Gene Regulatory Network Resets the Human Germline Epigenome for Development.
Cell 161, 1453–1467. - Irie, N.#, Weinberger, L.#, Tang, W.W.C.#, Kobayashi, T., Viukov, S., Manor, Y.S., Dietmann, S., Hanna, J.H., and Surani, M.A.*, (#Equal contribution), (2015).
SOX17 is a critical specifier of human primordial germ cell fate. (Best of Cell 2015)
Cell 160, 253–268.