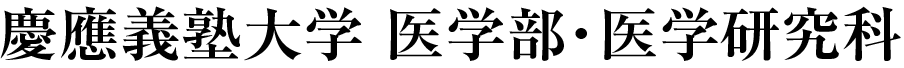柚﨑 通介Michisuke Yuzaki
ヒト生物学-微生物叢-量子計算研究センター (Bio2Q)
特任教授
学位
| 1983年 | 情報処理技術者資格取得 |
|---|---|
| 1985年 | 医師免許取得 |
| 1985年 | ECFMG(米国海外医学部卒業認定資格)取得 |
| 1993年 | 医学博士(自治医科大学) |
主な研究領域
中枢神経系・腸管神経系・自律神経系・末梢神経系におけるシナプス形成機構
シナプス異常でおきる病態の解明と治療法の開発
略歴
| 1985年 | 自治医科大学医学部卒業 |
|---|---|
| 1985-1989年 | 大阪府立総合医療センター・大阪府衛生部 |
| 1989-1993年 | 自治医科大学大学院博士課程 |
| 1992-1993年 | 日本学術振興会・特別研究員 |
| 1993-1995年 | 米国ロッシュ分子生物学研究所・HFSP長期海外研究員 |
| 1995-2002年 | 米国セントジュード小児研究病院・助教授 |
| 2002-2003年 | 米国セントジュード小児研究病院・准教授 |
| 2003年-2025年 | 慶應義塾大学医学部・生理学教授 |
| 2021-2023年 | 慶應義塾大学大学院・医学研究科委員長 |
| 2025年 | 慶應義塾大学 ヒト生物学-微生物叢- 量子計算研究センター (Bio2Q) 特任教授・拠点長特別補佐 |
受賞・特許
| 2005年 | 北里賞 |
|---|---|
| 2012年 | 時實利彦記念賞 |
| 2013年 | 文部科学大臣表彰(科学技術賞) |
| 2023年 | 内藤記念科学振興賞 |
| 2023年 | 紫綬褒章 |
| 2024年 | 上原賞 |
研究内容
私たちの脳は、視覚や聴覚、運動などのさまざまな機能を担う「神経回路網」によって構成されています。この神経回路は、約1,000億個もの神経細胞が、「シナプス」と呼ばれる結び目のような構造で互いにつながることで成り立っています。1つの神経細胞には平均して1万個ものシナプスが存在するとされ、脳全体のシナプスの数はおよそ1,000兆個に達すると考えられています。
シナプスは、遺伝子だけでなく、生まれた後の環境や経験、学習などによって生涯を通じて変化していきます。こうした変化こそが、記憶や学習の基盤です。また、うつ病や統合失調症、自閉スペクトラム症、アルツハイマー病といったさまざまな精神・神経疾患は、シナプスの異常が原因で起こる「シナプス病」と考えられています。そのため、シナプスがどのようにして作られ、保たれ、失われていくのかを解明することは、病気の理解や新しい治療法の開発に直結する重要な課題です。

私たちのグループは、もともと免疫の分野で知られていた「補体C1q」に似た分子(補体ファミリー分子)が、脳の中でシナプスをつくる働きを持っていることを世界で初めて発見しました。たとえば、小脳では、神経活動に応じて「Cbln1」という分子が分泌され、シナプス前部の分子(ニューレキシン)と後部の分子(GluD2)を同時につなぐことで、シナプスの形成や維持を助けていることがわかりました。

その後も、私たちはC1ql1という分子が小脳の登上線維のシナプスを制御していることや、C1ql2やC1ql3が海馬の神経細胞でカイニン酸受容体の集まり方を決めていることを明らかにしてきました。これらの補体ファミリー分子は、脳だけでなく末梢神経系や腸の神経系にも存在し、さまざまな病気に関わっていると考えられます。
さらに私たちは、これらの知見をもとに「人工シナプスコネクター」の開発にも取り組んでいます。たとえば、グルタミン酸受容体と結合する「Nptx1」という分子の構造を解析し、小脳でシナプスをつくる能力が高い「Cbln1」と組み合わせて、「CPTX」という新しい人工シナプス形成分子(シナプスコネクター)を開発しました。CPTXは、小脳だけでなく、さまざまな神経回路でもシナプスをつくることができ、小脳失調症やアルツハイマー病、脊髄損傷のマウスモデルでは、CPTXを投与することで運動機能や記憶機能が数日以内に改善するという成果が得られています。
今後、このような人工シナプスコネクターの技術が、自閉スペクトラム症や統合失調症、アルツハイマー病などの「シナプス病」に対する新しい治療法につながることが期待されます。

代表論文
- Nozawa K, Sogabe T, Hayashi A, Motohashi J, Miura E, Arai I, Yuzaki M*. In vivo nanoscopic landscape of neurexin ligands underlying anterograde synapse specification. Neuron 110:3168-3185, 2022.
- Suzuki K, Elegheert J, Song I, Sasakura H, Senkov O, Matsuda K, Kakegawa W, Clayton AJ, Chang VT, Ferrer-Ferrer M, Miura E, Kaushik R,Ikeno M, Morioka Y, Takeuchi Y, Shimada T, Otsuka S, Stoyanov S, Watanabe M, Takeuchi K, Dityatev A*, Aricescu AR*, Yuzaki M*. A synthetic synaptic organizer protein restores glutamatergic neuronal circuits. Science 369:eabb4853, 2020.
- Ibata K, Kono M, Narumi S, Motohashi J, Kakegawa W, Kohda K, Yuzaki M.* Activity-dependent secretion of synaptic organizer Cbln1 from lysosomes in granule cell axons. Neuron 102:1184-1198, 2019.
- Kakegawa W, Katoh A, Narumi S, Miura E, Motohashi J, Takahashi A, Kohda K, Fukazawa Y, Yuzaki M*, Matsuda S*. Optogenetic control of synaptic AMPA receptor endocytosis reveals roles of LTD in motor learning. Neuron 99:985-998, 2018.
- Elegheert J, Kakegawa W, Clay JE, Shanks N, Behiels E, Matsuda K, Kohda K, Miura E, Rossmann M, Mitakidis N, Motohashi J, Chang VT, Siebold C, Greger IH, Nakagawa T, Yuzaki M*, Aricescu AR*. Structural basis for integration of GluD receptors within synaptic organizer complexes. Science 353:295-299, 2016
- Matsuda K, Budisantoso T, Mitakidis N, Sugaya Y, Miura E, Kakegawa W, Yamasaki M, Konno K, Uchigashima M, Abe M, Watanabe I, Kano M, Watanabe M, Sakimura K, Aricescu AR, Yuzaki M*. Trans-synaptic modulation of kainate receptor functions by C1q-like proteins. Neuron 90:752-767, 2016.
- Kakegawa W, Mitakidis N, Miura E, Abe M, Matsuda K, Takeo YH, Kohda K, Motohashi J, Takahashi A, Nagao S, Muramatsu SI, Watanabe M, Sakimura K, Aricescu AR, Yuzaki M*. Anterograde C1ql1 signaling is required in order to determine and maintain a single-winner climbing fiber in the mouse cerebellum. Neuron 85:316-329, 2015.
- Ito-Ishida A, Miyazaki T, Miura E, Matsuda K, Watanabe M, Yuzaki M*, Okabe S*. Presynaptically released Cbln1 induces dynamic axonal structural changes by interacting with GluD2 during cerebellar synapse formation. Neuron 76:549-564, 2012.
- Unoki T, Matsuda S, Kakegawa W, Van UT, Kohda K, Suzuki A, Funakoshi Y, Hasegawa H, Yuzaki M*, Kanaho Y*. NMDA receptor-mediated PIP5K activation to produce PI(4,5)P2 is essential for AMPA receptor endocytosis during LTD. Neuron 73:135-148, 2012.
- Kakegawa W, Miyoshi Y, Hamase, K, Matsuda S, Matsuda K, Kohda K, Emi K, Motohashi J, Konno R, Zaitsu K, Yuzaki M*. D-Serine regulates cerebellar LTD and motor coordination through the delta2 glutamate receptor. Nature Neurosci 14:603-611, 2011.
- Matsuda K, Miura E, Miyazaki T, Kakegawa W, Emi K, Narumi S, Fukazawa Y, Ito-Ishida A, Kondo T, Shigemoto R, Watanabe M, Yuzaki M*. Cbln1 is a ligand for an orphan glutamate receptor δ2, a bidirectional synapse organizer. Science 328:363-368, 2010.
- Matsuda S, Miura E, Matsuda K, Kakegawa W, Kohda K, Watanabe M, Yuzaki M*. Accumulation of AMPA Receptors in Autophagosomes in Neuronal Axons Lacking Adaptor Protein AP-4. Neuron 57:1-16, 2008.
- Hirai H, Pang Z, Bao D, Miyazaki T, Li L, Miura E, Parris J, Rong Y, Watanabe W, Yuzaki M*, Morgan JI*. Cbln1 is essential for synaptic integrity and plasticity in the cerebellum. Nature Neurosci 8:1534-1541, 2005.
- Hirai H*, Launey T, Mikawa S, Torashima T, Yanagihara D, Kasaura T, Miyamoto A, Yuzaki M*. New role of δ2-glutamate receptors in AMPA receptor trafficking and cerebellar function. Nature Neurosci 6:869-876, 2003.
- Kohda K, Wang Y, Yuzaki M*. Mutation of a glutamate receptor motif reveals its role in gating and δ2 receptor channel properties. Nature Neurosci 3:315-322, 2000.
論文指導資格の有無