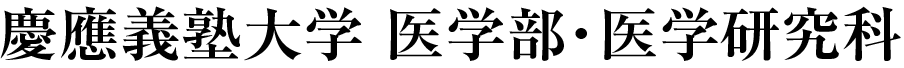山上 亘Wataru Yamagami
産婦人科学(婦人科)教室
教授
学位
主な研究領域
略歴
| 2000年3月 | 慶應義塾大学医学部卒業 |
|---|---|
| 2000年4月 | 慶應義塾大学医学部産婦人科 研修医 |
| 2002年6月~2004年4月 | 関連病院へ出向 |
| 2004年5月~2005年3月 | 慶應義塾大学病院産婦人科助手 |
| 2005年4月~2008年3月 | 国立がんセンター研究所病理部リサーチレジデント |
| 2009年4月~2011年3月 | 国立病院機構東京医療センター産婦人科 医員 |
| 2011年4月~2018年12月 | 慶應義塾大学医学部産婦人科 助教 |
| 2019年1月~ | 慶應義塾大学医学部産婦人科 専任講師 |
| 2023年4月~ | 慶應義塾大学医学部産婦人科 教授 |
受賞・特許
| 2011年 | 第49回日本癌治療学会学術集会優秀演題賞 |
|---|---|
| 2014年 | 第52回日本癌治療学会学術集会優秀演題賞 |
| 2016年 | 第68回日本産科婦人科学会学術集会JSOG Congress Encouragement Award |
| 2019年 | Journal of Gynecologic Oncology Best Reviewer Award |
| 2020年 | 日本産科婦人科内視鏡学会優秀査読者賞 |
主な研究内容
1.子宮体癌/子宮内膜異型増殖症の妊孕性温存療法
子宮体癌およびその前がん病変である子宮内膜異型増殖症(AEH)の標準治療は子宮全摘出術を含む手術療法であり、妊孕性は完全に消失する。それに対する妊孕性温存療法として酢酸メドロキシプロゲステロンを用いた高用量黄体ホルモン療法がある。治療対象は子宮内膜に限局する高分化類内膜癌(G1)またはAEHである。当科は本邦でも多数の高用量黄体ホルモン療法の経験を有しており、初回治療例の病変消失率はAEHで98%、G1で93%であり、パートナーを有する症例の妊娠率は40-50%である。本治療の難点は再発率の高さにあり、AEHの44%、G1の69%で再発を経験する。しかしながら、症例を選択すれば、再度の妊孕性温存が可能であり、AEHで95%、G1で97%、再度の病変消失を経験している。当科では現在、至適フォローアップ方法の確立や、遺伝子パネルシーケンスや免疫組織化学を用いた効果/予後予測モデルの開発を行うとともに、婦人科悪性腫瘍研究機構(JGOG)およびそれに所属している多機関と連携のうえ、子宮体癌や子宮内膜異型増殖症に対する妊孕性温存療法後の子宮内再発に対する再度の妊孕性温存療法の第II相試験を進めている。

2.子宮体癌に対する低侵襲手術:センチネルリンパ節生検
子宮体癌は比較的予後良好の悪性腫瘍である。従来は、開腹手術が主流であったが、現在は早期癌に対しては腹腔鏡下手術やロボット支援下手術といった鏡視下手術が主流となりつつある。子宮体癌の標準術式の一部として領域リンパ節郭清が行われることがあり、鏡視下手術においても施行可能であるが、リンパ浮腫やリンパ嚢胞といった有害事象の原因となるため、長期にわたる患者のQOLの低下につながる可能性がある。それを回避する1つの方法としてセンチネルリンパ節(SN)ナビゲーション手術がある。SNは見張りリンパ節とも呼ばれ、そのリンパ節に転移が認められなければ、他のリンパ節にも転移が認められない。すなわち、そのリンパ節を調べることで、無用な領域リンパ節郭清を回避できるという治療法である。当科での子宮体癌を対象とした臨床研究ではSNの同定率は98%、感度や陰性反応的中率はともに100%であり、SN生検を用いた子宮体癌手術の可能性が示された。
2023年4月現在、乳がんや悪性黒色腫では保険適用となっているが、子宮体癌や子宮頸癌、外陰癌に対しても、一部のトレーサーの保険収載が認められ、婦人科領域への実臨床への適応拡大が見込まれている。



Yamagami W et al. Int J Gynecol Cancer 2017
代表論文
- Yamagami W, Susumu N, Banno K, Hirao T, Kataoka F, Hirasawa A, Suzuki N, Aoki D, Nozawa S. Clinicopathologic manifestations of early-onset endometrial cancer in Japanese women with a familial predisposition to cancer. J Obstet Gynaecol Res. 2005;31:444-451
- Yamagami W, Susumu N, Tanaka H, Hirasawa A, Banno K, Suzuki N, Tsuda H, Tsukazaki K, Aoki D. Immunofluorescence-detected infiltration of CD4+FOXP3+ regulatory T cells is relevant to the prognosis of patients with endometrial cancer. Int J Gynecol Cancer. 2011;21:1628-1634
- Tomisato S, Yamagami W, Susumu N, Kuwahata M, Takigawa A, Nomura H, Kataoka F, Hirasawa A, Banno K, Aoki D. Clinicopathological study on para-aortic lymph node metastasis without pelvic lymph node metastasis in endometrial cancer. J Obstet Gynaecol Res. 2014;40:1733-1739
- Yamagami W, Susumu N, Ninomiya T, Nakadaira N, Iwasa N, Kuwahata M, Nomura H, Kataoka F, Banno K, Aoki D. Hysteroscopic transcervical resection is useful to diagnose myometrial invasion in atypical polypoid adenomyoma coexisting with atypical endometrial hyperplasia or endometrial cancer with suspicious myometrial invasion. J Obstet Gynaecol Res. 2015;41:768-775
- Ninomiya T, Yamagami W, Susumu N, Makabe T, Sakai K, Wada M, Takigawa A, Chiyoda T, Nomura H, Kataoka F, Hirasawa A, Banno K, Aoki D. Retrospective Analysis on the Feasibility and Efficacy of Docetaxel-Cisplatin Therapy for Recurrent Endometrial Cancer. Anticancer Res. 2016;36:1751-1758
- Kataoka F, Susumu N, Yamagami W, Kuwahata M, Takigawa A, Nomura H, Takeuchi H, Nakahara T, Kameyama K, Aoki D. The importance of para-aortic lymph nodes in sentinel lymph node mapping for endometrial cancer by using hysteroscopic radio-isotope tracer injection combined with subserosal dye injection: Prospective study. Gynecol Oncol. 2016;140:400-404
- Yamagami W, Susumu N, Kataoka F, Makabe T, Sakai K, Ninomiya T, Wada M, Nomura H, Hirasawa A, Banno K, Nakahara T, Kameyama K, Aoki D. A Comparison of Dye Versus Fluorescence Methods for Sentinel Lymph Node Mapping in Endometrial Cancer. Int J Gynecol Cancer. 2017;27:1517-1524
- Yamagami W, Susumu N, Makabe T, Sakai K, Nomura H, Kataoka F, Hirasawa A, Banno K, Aoki D. Is repeated high-dose medroxyprogesterone acetate (MPA) therapy permissible for patients with early stage endometrial cancer or atypical endometrial hyperplasia who desire preserving fertility? J Gynecol Oncol. 2018;29:e21
- Yamagami W, Nagase S, Takahashi F, Ino K, Hachisuga T, Mikami M, Enomoto T, Katabuchi H, Aoki D. A retrospective study for investigating the relationship between old and new staging systems with prognosis in ovarian cancer using gynecologic cancer registry of Japan Society of Obstetrics and Gynecology (JSOG): disparity between serous carcinoma and clear cell carcinoma. J Gynecol Oncol. 2020;31:e45
- Saotome K, Yamagami W, Machida H, Ebina Y, Kobayashi Y, Tabata T, Kaneuchi M, Nagase S, Enomoto T, Aoki D, Mikami M. Impact of lymphadenectomy on the treatment of endometrial cancer using data from the JSOG cancer registry. Obstet Gynecol Sci. 2021;64:80-89
- Sakai K, Yamagami W, Machida H, Ebina Y, Kobayashi Y, Tabata T, Kaneuchi M, Nagase S, Enomoto T, Aoki D, Mikami M. A retrospective study for investigating the outcomes of endometrial cancer treated with radiotherapy. Int J Gynaecol Obstet. 2022;156:262-269
- Makabe T, Yamagami W, Hirasawa A, Miyabe I, Wakatsuki T, Kikuchi M, Takahashi A, Noda J, Yamamoto G, Aoki D, Akagi K. Incidence of germline variants in Lynch syndrome-related genes among Japanese endometrial cancer patients aged 40 years or younger. Int J Clin Oncol. 2021;26:1767-1774
- Yoshimura T, Yamagami W, Takahashi M, Hirano T, Sakai K, Makabe T, Chiyoda T, Banno K, Aoki D. Clinical Usefulness of Endometrial Cytology in Determining the Therapeutic Effect of Fertility Preserving Therapy. Acta Cytol. 2022;66:106-113
- Matoba Y, Yamagami W, Chiyoda T, Kobayashi Y, Tominaga E, Banno K, Aoki D. Characteristics and clinicopathological features of patients with ovarian metastasis of endometrial cancer: a retrospective study. J Obstet Gynaecol. 2022 2:1-7